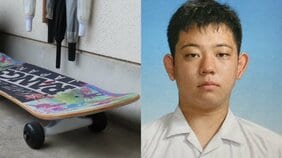真似をしてもらえることは、売り場の棚の拡充につながることも
——2017年に立ち上げられたコンテンツ戦略室は”アベンジャーズ”とも名高い精鋭軍団だと聞いています。
当初3名からスタートし、現在は7名が所属しています。他の部署は、参考書、図鑑など、作る本のジャンルが決まっているんですが、我々の部署には、そういう定まったジャンルはなく、各個人がそれぞれテーマをもって作る本を決めています。
つまり、どんなジャンルの本でも作ることができます。それゆえ、自身の確固たるプリンシプル(原理や原則)を持っている人が多く、みんな個性的です。
結果的に、私は、7割くらいが「児童書」になりますが、現在も学習参考書や一般書なども作っています。3〜4月は、7冊の学習参考書を発刊します。
——それらの他ジャンルの経験が、児童書に生かされているところもありますか?
もちろん、あります。参考書を作っていた当時、読者から『説明がヘタで、わかりづらい』というストレートな声が届きました。そこから、読みやすくてワクワクする文章とは?と追求し、たどり着いたのが『読者と対話をしているような文章を書く』ということでした。
たとえば、この文章を読んだあとに『きっとこんな疑問が生じるだろう』と考えながら、次の文章ではその疑問点を補足する文章を書く。
単にすべてを説明するのではなく、あえて読者に疑問を抱かせるような書き方をして、次の文でその疑問点を解消する。そうすることで、読者は本と対話をしているような感覚をもつことができます。
読みやすくて楽しいのは、興味を持たせ惹きつけて解決できる、そういう本ではないかと感じ、本書でも合間のコラムなどで意識して書いています。
——児童書を作る上での目黒さんのプリンシプルとは?
児童書は、いかに棚をとっていくかという陣取り合戦のようなところがあります。1冊で100万部売れることも重要ですが、5万部ずつ20冊売れる本を作れば、「棚をとる」ことができ、それは長く本を売るための最大の戦略になります。
そういう意味では、弊社だけの書籍では、棚形成に限界があるので真似をしてもらえることは売り場の棚の拡充につながり、ありがたいことでもあるんです。もちろん、同時に、苦々しい気持ちにもなりますが…。
ただし、本は、「ヒットしなければ意味がない」とは思っていません。少ないコアなファン層に深く刺さる。それも充分に価値のある本ですし、改善点が見えれば次作に生かせるかもしれない。
今の私が楽しめるもの、固定概念にとらわれない本を今後も作っていきたいですね。
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班


















![国際[最強王図鑑]協会公式会員証(写真提供/Gakken)](https://shuon.ismcdn.jp/mwimgs/7/d/744mw/img_7d747eece7cf4ec5043b3e183aec8ef0223048.jpg)