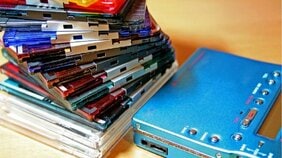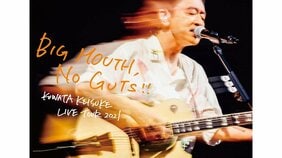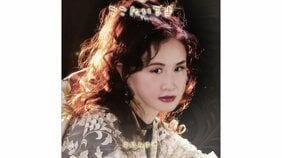ひとむかし前、唄は人生の一部だった
徳島県の山間部にある那賀町(なかちょう)が、数年前なんと町でCDを出した。地元の民謡や祝い唄、田植え唄などを収録したこの『阿波の遊行』は、発売からしばらくするとミュージシャンの間で話題になりAmazonランキングでも上位に昇った。
この音源は1960年代から20年間、現代舞踊家の檜瑛司(ひのきえいじ)さんが四国をまわり村に残る民謡をフィールドワーク的に収録したもので、亡くなったあと、家族により役場に寄贈され、そこから久保田麻琴さんによって再編集された。
那賀町役場の柔軟さよ! 四国にとって大切な資料が、私たちの手に届く形になったことに感動した。
聴いてみると、音楽というよりも唄が暮らしに必要不可欠なものであったことが見えてくる。たとえば収録されている『美郷の田植え唄』や『牟岐の麦打ち唄』は、労働から唄ができている。作業の息を合わせるために自然に生まれた唄だろう。日本人は農耕民族だから、全国いろんなところに田植え唄が残っている。
我が家も代々農家で、田植え機や稲刈り機といった農機具のない時代は、水田に大きな立方体の木の定規のようなものをあてて、そこへ数名が一列に並んで唄を歌いながら苗を植えていたそうだ。
そうするとピッタリと苗の位置を揃えることができた。定規を前へ進ませ、歌で息を揃えて田植えをしたのだと祖母から聞いた。
つまり、労働効率を上げるための田植え唄だったのだ。想像するとなんと美しい光景。でも、ずっと手作業で腰が痛かっただろうなあ。祖母の代の女性はみんな腰が曲がっていて「よく働いた証だ」と言われた。
いま私は百姓もしているので、少しは農作業のしんどさもわかるのだけれど、機械化が進んで救われたのは農家の女性だろう。
そんなきつい農作業が、田植え唄により少しは楽しくなったのではないか。あの時代の人はいつでも唄を携えていた。家でも、銭湯でも、畑でも、祭りでも。祖父母も近所の人たちも、玄関先に集まればみんなすぐ歌っていた。カラオケに行かずとも、唄は人生の一部だった。
農業をはじめ、林業や漁業など大人数が協力しないとできない第一次産業には労働歌が必要不可欠な道具だったのだと思う。また、しんどい労働のあと、お酒を一杯やりながら皆で歌うためでもあったと祖父が言っていた。
今は、ほとんど機械化され、大量生産できる時代になったので、労働歌や掛け声は消滅しつつあるが、畑のチームでバンドをやりながら、唄がチームの心を繋いでいるなとも感じている。
民族音楽としても、檜さんの残した音源はとても価値のあるものだ。労働歌には、プロのミュージシャンが歌うのとはまた違った力強さと、説得力、生命を燃やす人間の色気を感じる。こういった唄の多くも口承だったため、書いたものが残っていなかったりするのだ。