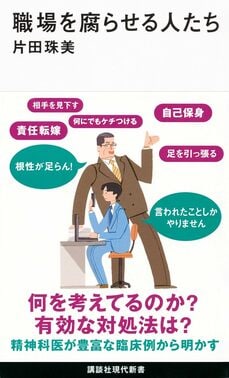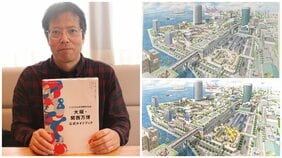④ 自分が悪いとは思わない
職場を腐らせる人を変えるのが困難な一因として、自分が悪いとは思わないことが挙げられる。第1章で紹介した事例の多くは、周囲が注意しようが、辟易しようが、同じことを繰り返している。これは、受信器の感度が少々低いせいではないかと疑いたくなるが、それだけではないだろう。自分の落ち度を決して認めたくなくて、自己正当化のメカニズムが働くせいでもある。
自己正当化は嘘よりも厄介だ。なぜかといえば、嘘をついている人には、その自覚があるが、自己正当化は知らず知らずのうちに行われ、その自覚がないからだ。当然、自分が悪いとは思わないし、反省も後悔もしないので、同じことを繰り返す。
この傾向、つまり反復強迫は、自己正当化が功を奏して周囲から許容されたり黙認されたりした過去の成功体験が大きいほど強まるように見受けられる。
もっと厄介なのは、自分には「例外」を要求する権利があるという思いが確信にまで強まっているタイプであり、フロイトは〈例外者〉と名づけた(「精神分析の作業で確認された二、三の性格類型」)。〈例外者〉は、法律あるいは世間一般の常識では許されないようなことでも自分だけは許されると思い込みやすい。
もちろん、通常はそんな「例外」を認めてもらえるわけがない。そこで、自分だけが「例外」を要求することを正当化する理由が必要になる。それを何に求めるかというと、ほとんどの場合自分が味わった体験や苦悩である。
このような体験や苦悩の責任は自分にはないと〈例外者〉は考える。必然的に、自分には責任のないことで「もう十分に苦しんできたし、不自由な思いをしてきた」のだから、「不公正に不利益をこうむった」分、「特権が与えられてしかるべきだ」との認識を持ちやすい。
ここで重要なのは、本人が味わったと主張する体験や苦悩が、客観的に見てどうかはあまり意味がないことだ。〈例外者〉は、自分の体験や苦悩が耐えられないほどつらく、過酷だったので、自分だけは「例外」を要求しても許されると思い込んでいる。
だから、普通の人なら遠慮するようなことでも、自分だけは実行する権利があり、許されて当然と考える。あるいは、みなに課されている義務であっても、自分だけは免除してほしいと要求する。その結果、職場を腐らせることを繰り返し、いくら迷惑をかけても、自分が悪いとは思わない。もちろん、決して謝らない。
写真/shutterstock