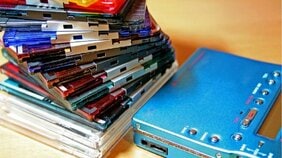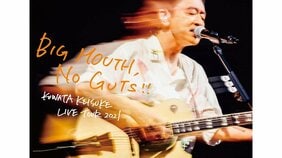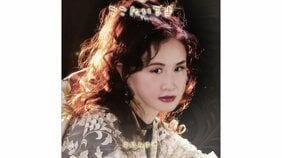米津玄師の曲が「懐かしい」のはどうしてか
さて、『蛍の光』はスコットランド民謡、『蝶々』はドイツ民謡、『あおげば尊し』もアメリカの曲なんです。となると、訳詞を載せないといかんということですね。
7・5調(※7音・5音の順番で繰り返す形式 「ほたるのひかり まどのゆき」など)や8・5調(同8音・5音の順で繰り返す)がほとんどの日本で、『蝶々』は6・7・8・7。『あおげば尊し』は8・7。
原曲の意味も残しつつ、四苦八苦しながら作詞したのだろうと思う。
続いて、『赤とんぼ』や『かたつむり』などの、童謡やわらべうたの多くは祖父が生まれた大正時代に作られている。この多くも五音音階で作られる。
江戸時代までは、雅楽や能、歌舞伎などのアジアの影響を受けた音楽だったのが、開国以降は西洋音楽の流れになったので、まずは扱いやすい五音音階を取り入れたのだろう。日清戦争以降、今度は軍歌を歌うことになるが、これもやはり5音なのだ。
この五音音階に懐かしさを感じるのは、きっとどの国の人も同じなんだろう。単純に口ずさみやすいし覚えやすいもの。7音という高度な音楽が浸透するまでは、世界中みんな5だったのでしょう。
五音音階を使った洋楽で真っ先に思い出すのは、レニー・クラヴィッツの『Rock and Roll is Dead』の頭のリフ。ペンタトニックは弦の押さえやすさもあります。現代のポップスでも実は多いのです。
キリンジ『エイリアンズ』や、くるり『言葉はさんかくこころは四角』、Perfume『レーザービーム』、星野源『恋』も五音音階です。
他にも、米津玄師は『パプリカ』他たくさんの楽曲で五音音階を使っています。坂本九さんの『明日があるさ』もそうですね。
共通して、覚えやすさ、歌いやすさがあり、ポップなのに懐かしさも感じる。日本独自の音階ではないにしても、100年以上愛されているのだから、〝日本的〞を感じるのは私だけではないはずだ。
松任谷由実さんの『春よ、来い』もサビでは五音音階になり、さらにAメロは7・5調になる。この曲の「和」のイメージは、語感と音律、両方の見事な合わさりによるものだと思うのだ。
ということで、言葉だけを切り離して考えるなかれ。すべてが一つの穴の中から湧き出て、いろんな分野に分かれたのだ。
写真/shutterstock