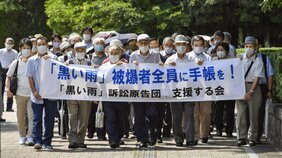美しければ美しいほど「野蛮」
私は、哲学者テオドール・アドルノの「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である」という言葉を想起しながら、この映画を鑑賞せずにはいられなかった。アドルノの言葉が意味したのは、アウシュヴィッツだけではなく、ホロコースト一般とそれに類する大虐殺の後に詩(美しいもの)を作り出し、鑑賞することはホロコーストの悲惨を生み出した文化の肯定でしかなく、野蛮な行為だということである。
広島と長崎への原爆投下についても同じことが言える。そしてとりわけ、映画を一編の交響曲のように、あるいは詩のように緊密な美しさに仕上げることに長けたノーラン監督がロバート・オッペンハイマーについての伝記映画を作ったのだから、この映画は完成度が高ければ高いほど、美しければ美しいほど、「野蛮」であることは避けられない。
それでもなお、私はこの映画が公開されたことを歓迎したい。というのは、私たちの世界にはそのような野蛮さが確かに存在するし、そこから(公開しないことによって)目を逸らしてはならないと思うからだ。
本記事では内容(といってもオッペンハイマーの伝記がベースになっているので、ほぼ周知の内容であるが)にはなるべく踏み込まずにこの映画の見方を提示しつつ、それに関連して少々深く、すでに批判のある「広島・長崎の不在」について考えてみたい。
本作を少しだけ難解にしているのは、時系列通りに展開しない構成である。終戦後の1954年、マッカーシズム(赤狩り)の猛威の中で、ソ連のスパイ疑惑で公聴会にかけられるオッペンハイマーと、大学生時代から長じてロスアラモスでの原爆開発、そしてプリンストン高等研究所の所長となったオッペンハイマーの姿が、パッチワークのように交互に描かれていく。
そのこと自体は、オッペンハイマーの大まかな伝記と戦前から戦後の世界史・アメリカ史のあらましを知っていれば、本作を理解する上でそれほど問題とはならない。