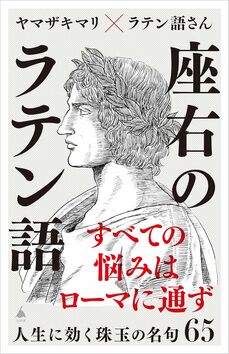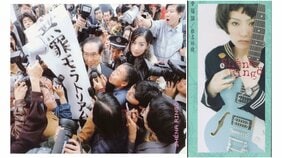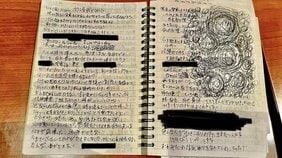民放も娯楽のひとつ
ラテン語 娯楽の強力さは、アウグスティヌスの『告白』にも描写されています。真面目だった青年が友達に誘われて剣闘士競技を見に行きます。
最初のうちは競技場には行っても見ないように見ないようにと気をつけて目を閉じているのですが、観客の歓声といった熱気に当てられて遂に目を開くと、そこからはもう一気に引き込まれ、競技場に通うようになる。そんな話が載っています。
ヤマザキ 結局は群集心理ですよね。長いものに巻かれ、大きなものの一部になることで得られる掛け値なしの安心感。集団と同じ価値観で同じものを楽しみたくなる同調心理。エンタメは、人気が大きいほど民衆を大きな塊にして、1つの大きな力にまとめる手段としても活用されるのです。
エンタメを国策にしている国もあるくらいですからね。政治力としては受け入れられなくても、文化であれば、自覚もないまま人々の暮らしに侵入してきますから。
ちなみに、サーカスの語源がラテン語のcircus「輪」で、円形劇場に由来するのを知らない人は多いと思います。
『オリンピア・キュクロス』という漫画ではオリンピックをテーマにして古代ギリシャ人が1960年代にタイムスリップする物語を描きましたが、古代の人にしてみれば、今でも当時とさして変わらぬ様子のスポーツ競技場があることにびっくりすると思いますよ。私なぞ、東京の国立競技場の前を通るたびにコロッセオの現代版だと思ってしまいますから。
ラテン語 競技や娯楽で市民の政治への関心を失わせるという。
ヤマザキ そうですね。そう考えると、現代世界における表層的な「情報」というやつも、今や人を操作するエンタメの一種でしょう。
ラテン語 例えば民放は、まったくお金を払わずに見られる娯楽です。
ヤマザキ でも古代ローマ時代も、コロシアムの国が仕掛ける催し物を胡散くさいと思ったり、嫌う人もいたんですよ。大プリニウスとか。あくまでマイノリティですけどね。
*注釈
カフェ・ベローチェ 首都圏を中心に展開する日本のカフェチェーン。
アウグスティヌス
354年~430年。神学者、司教。北アフリカ生まれ。マニ教を信奉していたが、新プラトン主義などの影響を受けてキリスト教に入信。教義の確立に寄与した。告白アウグスティヌスの自伝。マニ教入信など過去の過ちを告白し、キリスト教への回心を語る。
写真/shutterstock