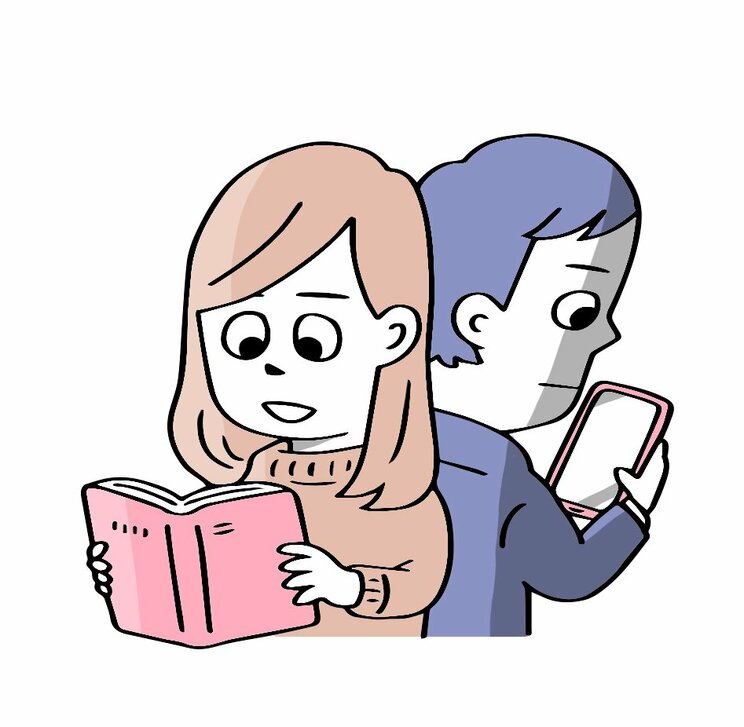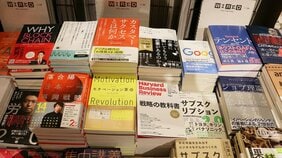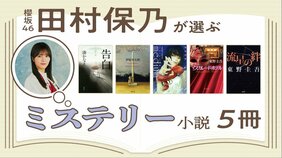あなたの「文化」は、「労働」に搾取されている
労働と文化の両立の困難に、みんなが悩んでいる。
その根底には、日本の働き方の問題があります。
具体的な例を挙げましょう。
たとえばフルタイムで働いている男性が育児に関わろうとすると、「育児休業」を取れ、と言われるでしょう。しかし本来、育児は子どもが家を出るまで十数年以上続きます。が、労働と育児を両立させる働き方の正解は、いまだに提示されていないのです。
あるいはコロナ禍を経て、政府は副業を推奨しています。しかし週5フルタイムで働いている人がそれ以外に副業をしようと思ったら、過労になりかねないはず。なぜ私たちはフルタイムの労働時間を変えずに、副業を推奨されているのでしょう?
現代の労働は、労働以外の時間を犠牲にすることで成立している。
だからこそ、労働と文化的生活の両立が難しいことに皆が悩んでいる。
──これは、現代日本を生きる私たちにとって、切実で困難な悩みなのです。
労働と文化を両立できる社会のために
しかし、現代日本に文句ばかり言っていても、話は進みません。
本書はまず、「なぜ私たちはこんな悩みを抱えているのか」という問いに挑んでみます。キーになるのは、近代以降の日本の働き方と、読書の関係です。あらゆる文化のなかでも、読書の歴史は長い。明治時代から日本人は読書を楽しんできました。さらに読書は、自分の人生を豊かにしたり楽しくしたりしようとする自己啓発の感覚とも強く結びついています(これについては第一章で詳しく書きます)。だからこそ労働と読書の関係の歴史を追いかけることによって、「なんで現代はこんなに労働と読書が両立しづらくなっているのか?」という問いの答えが導き出せるはずです。
そして最終的に本書は、「どうすれば労働と読書が両立する社会をつくることができるのか」という難題に挑みます。ぜひ最終章までたどり着いて、私の回答を読んでみてください。
本書は、日本の近代以降の労働史と読書史を並べて俯瞰することによって、「歴史上、日本人はどうやって働きながら本を読んできたのか? そしてなぜ現代の私たちは、働きながら本を読むことに困難を感じているのか?」という問いについて考えた本です。
どうすれば私たちは、働きながら、本を読めるのでしょう。
その問いを突き詰めると、結局ここにたどり着きます。
どういう働き方であれば、人間らしく、労働と文化を両立できるのか?
──私は、あなたと一緒に、真剣に「働きながら本を読める社会」をつくりたいのです。
これから、一緒に考えましょう。
なぜ働いていると本が読めなくなるのか?
文/三宅香帆