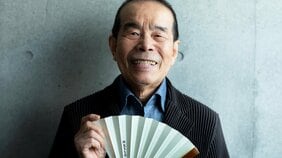技術を伝えず景色で伝えるディレクション
――斉藤さんが歌手として活動していくにあたっては、当時のポニーキャニオンのディレクターである長岡和弘さんの存在もとても大きかったと思います。「卒業」のレコーディングにあたっては、どんなアドバイスがあったんでしょうか?
長岡さんのディレクションって、多分普通とはちょっと違っていて、歌の技術的なことはあんまり言わないんです。
「校舎は木造で、下駄箱の下にはスノコが敷いてあって、下校のときにはそこで生徒たちが上履きを脱いでいる感じだね」みたいに、曲の背景にあるイメージを膨らませてくれるような言葉が多かったですね。「この日は青空だけど、ちょっと雲がぼんやり広がっているような天気かなあ」とか。
それは多分、歌う人の特性にあわせて言ってくれていたんだと思います。私は当時、俳優として先にデビューしていて、「歌をやりたい!」って強く思っていたわけじゃなかったんですよ。だから、そういう私の背景をわかってくれた上でアプローチしてくれた。それが私としてもすごく助かったし、とても感謝しています。
――歌う際には、現実の自分を投影するというより、あくまで物語の主人公を演じるような心づもりだったということでしょうか?
はい、そういう部分はあったと思います。ありがちな言い方になってしまいますけど、歌に同化するというより、自分の中のひとつのフィルターを通して物語を歌っているというか……。そのほうが、この歌が伝えようとしていることを、稚拙なりにも上手く掴めるんじゃないかと考えていたんだと思います。
――稚拙どころか、1曲のポップソングとして、すごく普遍的な魅力が備わっているように感じます。
「売れるものを作る」という視点だけだったら、長岡さんももっと直接的なディレクションをしたと思うんです。彼自身、甲斐バンドのベーシストとして下積み時代から長く音楽活動を行なってきた人だから、売上や実績の大切さもとてもよく理解していたと思います。
けれど、音楽を伝えるというのはそれだけじゃないよね、という気持ちも強くあったんじゃないでしょうか。ポニーキャニオンから私をデビューさせることになったときにも、私に対してそういう可能性を感じてもらえたのかもしれません。