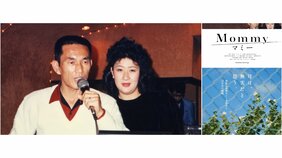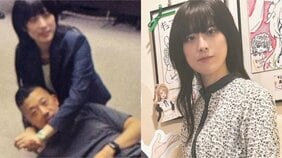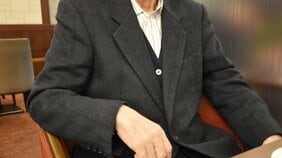でたらめな鑑定の連鎖
飯塚事件に話を戻す。捜査本部が足利事件の後を追うように科警研にMCT118法による鑑定を依頼したのは、1992年の夏ごろ。科警研から届いた鑑定結果では、被疑者も犯人も「16-26型」と判定された。これは足利事件と全く同じである。
合致するのは数百人に一人しかいないという鑑定法において、時空のかけ離れた二つの事件現場の試料がすべて同じ型であるなどということがあり得るのか。何かおかしい。
そして、その年の12月にはこの鑑定法の欠陥が東京の学会で公にされた。そのような鑑定を証拠として、逮捕に踏み切れるはずがない。当時、警察がほかの研究機関(=帝京大医学部)にミトコンドリア法など、別のDNA型鑑定を依頼していたのは、むしろ当然だったともいえる。
ところが、福岡県警はその後、1994年9月に久間氏を逮捕。起訴することになるのだが、そのとき裁判で検察が証拠として提出したのは、MCT118法による鑑定結果だけだった。
なぜか。帝京大での鑑定では、久間氏のDNAは、採取した犯人の試料(血液痕)と一致しなかったのである。この鑑定が正しければ、久間氏は無実だということになる。
このため、検察は、MCT118法の脆弱さは知りつつも、この鑑定結果を前面に押し立て、一方、被告人に有利な証拠となる帝京大の鑑定を隠して公判に臨んだのである。
久間氏の逮捕後、捜査本部はすぐに、令状によって久間氏の自宅の庭を掘り返している。この事件の証拠を探すためではなく、3年前に行方不明になった少女を見つけたかったのだと言われている。脆弱なMCT118法に代わる、決定的な証拠を見つけ出せると考えたのかもしれないが、それは徒労に終わった。
1995年から始まった第一審で、検察はMCT118法の他にDNA型鑑定があることを伏せていたが、弁護人の強い追及で仕方なく、その存在を認めた。そして、ミトコンドリア法などでの鑑定では久間氏のDNAは一致しなかったことが、はじめて明らかになった。
形勢は逆転したかに見えた。だが、この鑑定を行なった大学教授が、「試料が少なかった」と、信ぴょう性を自ら貶めるような証言をした。これが検察を救った。
のちにこの教授は、今になって言えるが、と前置きしながら、公判前に警察庁幹部が法医学教室にやってきて「科警研とそちらの鑑定は矛盾しないと法廷で証言してくれ。科警研のDNA鑑定は巨額の税金を投入しているので、間違っていたというのでは、困るのだ」と言われていたことを雑誌のインタビューで答えている。
1999年9月、福岡地裁は、MCT118法に軍配を上げ、久間氏に「死刑」を言い渡した。その後、2001年に控訴棄却、2006年に上告が棄却されて、久間氏の死刑が確定した。