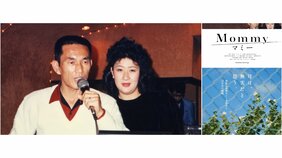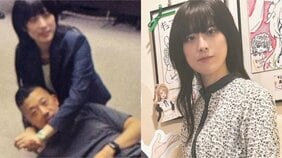「数百人に一人の確率」が一致
1980年代に、イギリス、アメリカ、日本などでDNA型鑑定を犯罪捜査に利用する試みが始まり、その成果を競い合っていた。そんな中で、1990年5月に足利事件(栃木県足利市)が発生した。
一時は迷宮入りも囁かれたが、DNA型鑑定によって犯人が割り出されたとして、大きなニュースとなった。このとき、科警研が行ったDNA型鑑定法がMCT118法である。
足利事件も、幼い女の子が何者かに連れ去られ、殺害された事件である。遺体の発見現場のすぐ横を流れる川の中から、女の子の衣類が見つかり、そこに犯人の精液が付着していた。
容疑者として目を付けられたS氏については、警察が一年間必死に張り込みを続けたが、別件逮捕の糸口さえ見つからず、捜査は難航した。このとき、捜査本部が頼ったのが、DNA型鑑定だった。
現場から採取した精液と、S氏の精液(ゴミで捨てられたティッシュペーパーから採取した)を科警研に送った。科学警察を標榜する警察庁は、この時期、DNA型鑑定の導入に熱心だった。そして鑑定の結果は警察庁を大いに喜ばせるものだった。
MCT118法によれば、犯人もS氏も、そのDNA型は16-26型。同じ型は数百人に一人の確率だという。
1991年12月、「DNA鑑定で一致」の記事が全国紙の一面に掲載されたその日の朝、S氏は初めて警察に呼ばれ、任意の取り調べを受けた。警察署の前には多くの人が集まり、その日のうちにS氏は自白に追い込まれた。
こうしてDNA型鑑定は華々しくマスメディアに登場したのだが、やがて、その綻びが露呈する。1992年12月、第一回のDNA 多型研究会が東京大学で開かれた。ここで、信州大学の研究チームが「科警研の行なっているMCT118法では正しい鑑定結果は出ない」という論文を公表した。
事件の中心的な証拠に大きな間違いが見つかったのだ。しかし、検察は宇都宮地裁で進んでいたS氏の裁判では一切その事実には触れず、1993年7月、法廷でS氏に無期懲役が言い渡されるのを平然と聞いていた。
科警研が間違いを認める論文を公表したのは一審判決の直後だった。1991年に行なわれた科警研の鑑定法では正確な型判定はできないことを、自ら認めた。抽出したDNAの鑑定数値(16-26)を測定するための当時のマーカー(物差し)が大雑把すぎて使い物にならなかったのである。
ただし、技術はまさに日進月歩で、この1993年の段階では、すでに新しいマーカーが導入されており、再鑑定をすれば、正しい測定値を得ることは可能であった。
ところが、科警研はここで開き直り、「古い鑑定結果は正確ではなかったが、そこに、2-4を足せば、新しいマーカーでの鑑定結果とだいたい同じになる」として、再鑑定をしないまま、犯人とS氏の「16-26型」を共に「18-30型」に訂正して「両者は一致する」と強弁し続けた。
これは科学ではない。数値が1違えば別人である。こんないい加減な主張が通るはずはないのだが、足利事件の控訴審の裁判官はこれを認めてしまった。