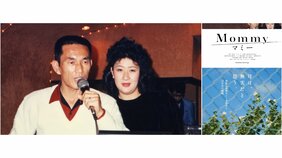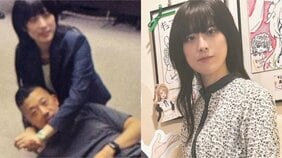再鑑定への道
飯塚事件の裁判と歩調を合わせるように、足利事件の裁判も進んだ。1993年から始まった控訴審で、科警研の技官が証人として出廷し、MCT118法について、正確ではないことを認めた。
しかし、中心的な存在だった女性技官は、追及する弁護人に対して開き直り、最後には「当時としては当然だったし、しようがなかったことだと思っております」と答えた。
彼らには、不正確な鑑定によって無辜の人を罪に陥れる可能性がある、という認識が完全に欠如していた。しかし、このやり取りを聞いても裁判官はMCT118 法に疑念を抱かず、1996年に控訴を棄却した。
裁判所に絶望した弁護団は、自分たちで再鑑定をすることにした。拘置所のS氏から毛髪を郵送で受け取り、日本大学医学部の押田茂實教授の手によって、新しいマーカーでのMCT118法による鑑定が実施された。
科警研の主張が「18-30型」であったのに対し、このとき出てきた数値は、「18-29型」だった。押田教授は「1つ違えば別人です。これは大変なことになったと思いました」と語った。
当時テレビ局でこの事件を追っていた私は、科警研の検査写真も、押田教授の検査写真も見ているが、雲泥の差であった。押田鑑定では、1目盛りごとに、くっきり見えたのに対し、科警研の写真では、16のところにも、26のところにも何も写っていなかった。
写真を見れば、どちらの鑑定が正確であるかは一目瞭然であった。押田教授の鑑定写真が、この事件が冤罪であることを、私に確信させてくれた。
だが、この押田教授の鑑定結果を見ても、裁判所は動こうとしなかった。2000年7月に最高裁が上告を棄却して、S氏の無期懲役が確定。さらに再審請求審でも、2008年2月、宇都宮地裁は「押田教授が鑑定したものが、本当にS氏の毛髪かどうか、分からない」として、請求を棄却した。
しかし、これにはマスメディアからも異論が相次いだ。世論に押されるような形で、2008年12月に東京高裁が再鑑定を決定した。そして、2009年4月、その結果が公表された。
S氏は「18-29型」、犯人(現場に遺留された精液)は「18-24型」、全くの別人だった。科警研の間違いを暴くのに18年の歳月を要した。検察の主張を鵜呑みにし続けた裁判所の責任は重い。そして、これは久間氏にとっても遅すぎた。この半年前に久間氏の死刑が執行されていた。