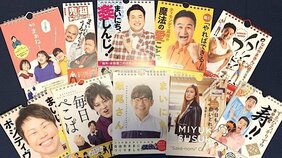ネガティブな感情をじっくり味わう
幸福を追えば現実への不満が募り、前向きを目指せば自己の本性と齟齬が出る。
まことに面倒な事実だが、それでは私たちはどうすればいいのか。この疑問については、幸いにも複数のデータが解決のヒントを示してくれている。
カリフォルニア大学の実験を見てみよう。研究チームは、1003人の男女に「悪い感情や間違った感情は、考えるべきでないと思う」のような文章に同意するかどうかを訊ね、全員の「受容傾向」を調べた。
受容傾向は、自分の感情を「よい/悪い」で判断せず、そのまま受け入れられるかどうかを表す特性のことだ。
たとえば、大事なテストを明日に控えた状況で、「私はだいぶ緊張している」とだけ思える人は、受容傾向が高い。一方で「緊張したらまずいから、リラックスしなければ」のように考える人は、受容傾向が低い。
こうして見ると、問題への対策を考えているぶんだけ、受容傾向が低い人のほうがよさそうにも思えるが、実験の結果はこうだった。
●受容傾向が高い人は、日常の不安が少なく、生活の満足度も高い。
●受容傾向が低い人は、嫌な体験を引きずりやすく、6ヵ月後もネガティブな記憶を保ち続けた。
心理学の世界には、「抑え込んだ感情は増加する」という基本原則がある。ネガティブな感情を抑えるためには、自分の内面に強く意識を向けざるを得ず、そのせいで逆に嫌な気分が強調されてしまうのが原因だ。泣き叫ぶ子供を鎮めようと怒ったら、かえって泣き声が大きくなったような状態に近い。
ノートルダム大学の心理学者キャシャー・ベリンダは、こう指摘する。
「ネガティブな感情を抑えつけると、思考や感覚の柔軟性が損なわれ、その後のタスクで問題が表面化する。逆説的ではあるが、感情を抑えようとすることは、その有害な効果をより長持ちさせることになる」
逆にネガティブな感情を受け止められる人は、自分の内面と無理に戦おうとはしないため、今の気分をただ観察するだけの余裕が生まれる。その姿勢がストレスの拡大を防ぎ、気分の波が自然と収まるのを待つこともできる。
つまり、本当に幸福感を得たいなら、まずは眼の前の不快さを否定せず、いったん受け入れる作業が必要になる。ネガティブな感情を敵にまわすことなく、味方につけようとする姿勢のほうが、結果として心を軽くしてくれるわけだ。
この考え方を実践する方法はシンプルで、ひとことでまとめるならこうなる。