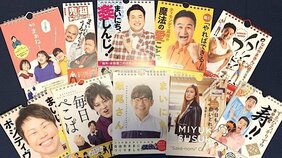意図的にポジティブに考えたときの2つの副作用
こういった副作用が起きるのには、主に二つのパターンがある。
1 ポジティブに考えることで、脳が自動的に「目標をやりとげた」と勘違いし、作業を行う気力がなくなる。
2 ポジティブに考えることで、脳が「そんなにうまくいくわけがない」と思い、作業を行う気力がなくなる。
まずひとつめは、私たちの脳が、頭の中に浮かべたイメージを真実だと思い込み、すでに目標を達成したかのように錯覚してしまうパターンだ。
よく知られるように、私たちの脳は、想像と現実を区別するのが苦手な器官だ。たとえば、ピアノを実際に演奏している人と、ピアノを演奏する自分の姿を頭の中でイメージしている人を調べた研究では、両者の脳の活動パターンに驚くほどの類似が見られた。
想像の世界でピアノを弾くと、現実での演奏とほぼ同じように、運動野や聴覚野などが動き出すのだ。
このデータが示すのは、私たちが思い浮かべる"想像"は、脳にとってはリアルな体験に近いという事実だ。理性では「これは現実ではない」と理解していても、感情に関わる深部のシステムは、そうした区別ができない。頭では「作り物だ」とわかっている怖い映画で心拍数が上がるのも、この脳の働きが原因だ。
そのため、「ポジティブな自分」ばかりを繰り返し頭に浮かべていると、脳は反射的に"本当に成功したような気分"を作り出す。この作用は私たちに一時的な満足感を与えてくれるが、その半面で「もう十分にやりきった」という誤ったフィードバックも生み、行動のモチベーションが下がってしまうわけだ。
そして、ポジティブシンキングで副作用が起きる二つめの原因が、前向きなことを考えようとした瞬間に、「そんなにうまくいくわけがない」や「それは理想論だ」といった否定的な声が頭の中に響くパターンだ。
将来の成功を思い描いたとたん、「今の自分では無理だ」と気持ちが冷めてしまった経験は多くの人に覚えがあるだろう。ポジティブな想像をしたせいで、理想と現実のギャップにあらためて気づかされる心理は、決して珍しいものではない。
この現象は自己肯定感が低い人ほど起こりやすく、ある研究でも、生まれつきネガティブな者にポジティブシンキングを使わせると、逆に不安が悪化したと報告している。
悲観的な人間が無理して前向きな態度を取ると、脳が「これは本当に私の思考なのだろうか」と脳が違和感を抱き始め、ネガティブな感情が増えてしまうらしい。つまり、根本がネガティブな人間にとって、ポジティブシンキングは自分を偽る行為にしかならないわけだ。