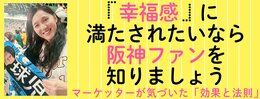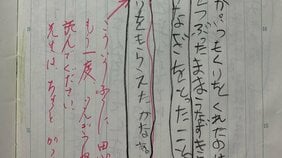「モンスターペアレント扱い」「学校の不手際でモンスターペアレントにされる」事例も…
そもそも、「モンスターペアレント」とはどのような保護者なのか。髙橋弁護士によれば、「不可能な要求を突きつけたり、自分の思い通りにならないことに対して感情的・暴力的に解消しようとしたりする保護者」がモンスターペアレントと言えるのではないかという。
さらに、悪質なものではこのような事例もあるという。
「『子どもがモンスターペアレントから追いかけ回される』『突然学校に乗り込んできて“この場で謝らせろ”と要求する』といったものから、登下校路で子どもの後をつけていき、自宅を特定したりする保護者もいます。さらには自宅に乗り込んできたり、登下校路で子どもに声をかけたりして、最終的にはやられた側の子どもが不登校になることもあります」
悪質化するモンスターペアレント問題。髙橋弁護士によれば、最近ではより複雑さを増し、保護者が「モンスターペアレント扱い」される事例や、意図せず「モンスターペアレントにされてしまった」といった保護者からの相談もあるという。
「『些細な問い合わせに対して、学校から回答に数週間かかると言われてしまった。以前自分が感情的になってしまったことがあったが、もしかしたら自分はモンスターペアレントとして扱われてしまっているのでは』と相談してこられる保護者がいます。
また、学校側の対応によってモンスターペアレントという扱いにされてしまう事例もあります。いじめ問題が起きたときに、学校の不手際で初期の調査をしないことがあります。事実が確認できていない状態で保護者が『いじめがあったので指導してほしい』と要望すると、学校から『あの保護者は事実もわからないのに指導しろと無理難題を吹っかけてきている』と“モンスターペアレント扱い”されてしまうのです。
しかし、初動の対応は学校側から正しい対応を提案しなければいけないはずです」
ほかにも、教員が嘘をついたり、問題を報告しないまま後任に引き継ぐ事例もあるという。
「保護者からアンケート調査の要望があった場合に、『上級の教員にも確認したんだけどやらないことになった』などと教員が嘘をつく事例があります。後で第三者委員会が調査を行なうと、そういう学校は忙しいことが多いのです。教員が多忙を極めるイベントシーズンなどにアンケート調査の要望が出た場合に、現場の判断で嘘をついてしまうのです。
また、高圧的な態度の教員もいます。保護者は怒って学校と話し合うことになるのですが、この教員が問題を学校に報告しないまま、後任の教員に引き継いだりしてしまうのです。引き継いだ教員からすると、保護者が怒っている理由が分かりません。結果として、その保護者はモンスターペアレントと呼ばれてしまう。このように不幸にしてモンスターペアレント扱いされている保護者もたくさんいます」
髙橋弁護士は、最後に「学校という大きな組織の運営である以上、外部で保護者からの意見を吸い上げるような場所を作ってもいいくらいだと思います。それを弁護士が請け負うのは、かなりの負荷を弁護士にかけてしまうのではないでしょうか」と懸念を示しつつ、制度を見守っていきたいと話した。
さまざまな問題が山積する教育現場。新たな取り組みが実を結ぶことを願うばかりだ。
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班