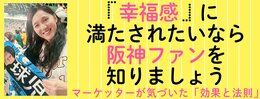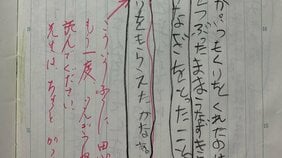目的は子どもたちの「教育を受ける権利」を守ること
制度の運用に向けて、大阪弁護士会では研修も行なったという。
「一般企業のカスタマーハラスメントであれば、『出禁』という対応が取れますが、保護者に対してそれはできません。学校と保護者は義務教育課程で長く関係が続きます。制度の概要説明とともに、このような教育現場の特殊性に由来する注意点や把握しておくべき法律問題を踏まえた研修を弁護士を対象に行ないました」
制度の課題と目的について、中嶋弁護士は次のように話した。
「『スクールアトーニー』の利用者である学校や教育委員会に制度を理解していただき、我々としては制度の広報をしていくことが課題です。あとは現場の予算です。行政は予算がつかないと、ニーズはあっても制度を利用できません。
制度の最終的な目的は、子どもたちの教育環境をよくすることだと考えています。先生方のメンタルを守り、負担を軽減することは、子どもたちの『教育を受ける権利』の実現にもつながります」
スクールアトーニー制度をめぐっては、その弊害について懸念する声もある。レイ法律事務所の髙橋弁護士は、「弁護士が前に出ることによって親の暴言に悩まされる教員が減ること」と期待する点を挙げたうえで、次のように懸念を示した。
「弁護士は法律には詳しいですが、人の話を丁寧に聞き、状況を細かく分析して理解する力は人によって差があります。保護者の悩みを教員から弁護士が引き継ぐことによって問題がバランスよく解決できると考えるのは、弁護士の能力に対する『過剰な期待』かもしれません」
さらに、弁護士が代理対応することのリスクについて次のように言及した。
「保護者は、学校の問題をうまく説明できないために感情に頼ってしまい、それがモンスターペアレントにつながっている部分があります。保護者の言うことを丁寧に汲み取れば、それが『適切な批判』である可能性もあるのです。
日頃から教員が心を砕いて聞き出している保護者の本当の悩みを、弁護士の介入で遮ってしまうことになるならば、結果的に学校側が今まで時間をかけて受け取っていた批判を“封殺”してしまう、という状況になりかねません」