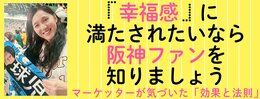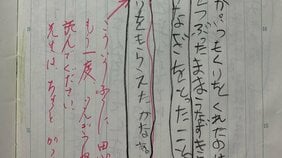大阪弁護士会が「スクールアトーニー」制度を立ち上げ
学校や教員に対する保護者等からの過剰な要求や不当要求への対応策として、このほど大阪弁護士会が「スクールアトーニー」と呼ばれる新たな制度を立ち上げた。大阪で従来取り組まれていた「スクールロイヤー」とは異なり、弁護士が学校や教員の代理人として保護者に直接対応できるのが特徴だ。
なお、文科省は学校問題全般に関わる弁護士をスクールロイヤーと総称しているが、大阪では助言型の「スクールロイヤー」が先行していたため、混同を避けるために「スクールアトーニー」の名称が使用された。
制度の立ち上げにも携わったアクト大阪法律事務所の中嶋弁護士はこう説明する。
「以前より、学校の教職員が保護者対応にかなり時間を割いており、これによって現場の教職員が疲弊しているということが問題視されており、文科省も弁護士等の専門家が教職員を支援する仕組みの構築を目指していました」
中嶋弁護士によれば、学校や教職員に対する不当要求の実態把握は2010年頃までには行なわれていたが、2024年に日弁連が弁護士による代理対応の必要性を盛り込んだ意見書(「教育行政に係る法務相談体制の普及に向けた意見書」)を出したことで、制度化の動きが進んだという。
「対保護者という観点で考えたときに、弁護士が学校側の代理人となることが子どもの『教育を受ける権利』の侵害につながる懸念があるため、弁護士が学校側で関与する際は『助言』にとどめるべきだ、というのがこれまでの日弁連の意見でした。
とはいえ、助言のみでは不当要求から教員を守ることができない場合もあります。また、弁護士は依頼者の正当な権利を擁護することが職責であり、『子どもの教育を受ける権利』にも配慮して対応することは当然であって、代理対応が否定される理由にはなりません。日弁連の意見書を受けて各弁護士会も制度構築を検討することとなり、大阪弁護士会でも制度の運用に関して大枠を決めました」
学校現場で起きる諸問題について助言を行なう助言型の「スクールロイヤー」とは異なり、スクールアトーニーはより踏み込んだ対応を行なうという。
「助言型のスクールロイヤーは『助言』までが役割ですが、スクールアトーニーは助言だけでなく『代理』対応まで行ないます。『教員がすぐに保護者対応を投げ出してしまうのではないか』という懸念の声がありますが、これは日常の現場教員の活動を把握していない暴論だと思います。
大阪以外でもすでに代理対応している実例もあり、先生方から『最後に助けてくれるところがあるから頑張れる』といった声もあると聞きます」
保護者による不当な要求の典型は長時間に及ぶ架電や面談要求、謝罪の強要や金銭要求などであり、ときには暴力を伴うものもある。
「5月に東京・立川の小学校で児童の保護者の知人による暴行事件がありました。あのような事件は当該児童だけでなく、現場に居合わせた児童も含めた多くの子どもたちの『教育を受ける権利』に影響します。教員が本来的な業務に専念できるような状況を戻すということも、社会正義の実現を使命とする弁護士の重要な役割だと思います」