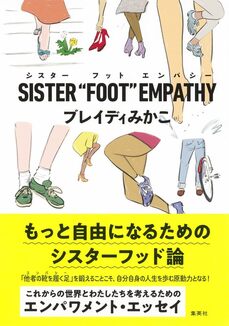アルゴリズムに支配された日々から抜け出すことがエンパシーにつながる
ーー昨今は多様性が叫ばれていますが、その中でエンパシーがより重要になっていく気がします。
世の中でよく耳にする多様性って、政治的な意味で使われることが多いですよね。でも、本来の意味を考えると、“いろんなものが、すでにそこにある状態”だと思うんです。
たとえば、今、目の前の机には緑茶もあれば、水も、コーヒーもある。それぞれがちがう飲み物だけど、いいも悪いもない。目の前にあるもので、どうにかうまくやっていこうよっていうのが、多様性の中で生きることだと思うんですね。
あるものは、ある状態のまま受け入れる。そんなある意味では乱雑な世界のほうが、実は生きやすい気もします。
とくにイギリスは移民の方も多いので、「これは許せない」「こうじゃなきゃ!」って、気にしていたらやっていけないんですよね。おもしろいもので、人って多様になるほど「まぁ、いっか」ってこだわらなくなって、寛容になる気がするんです。その「まぁ、いっか」の精神こそが大事。
「こうでなくてはいけない」のこだわりは手放したほうが気持ち的にも楽だし、結果、みんなの幸福度があがって生産性も上がるという、いいループが生まれるように思います。
ーー最後に…エンパシーにつながる、今日からでもできる日々の行動はありますか?
SNSとの関わり方を考えること。オックスフォード大学出版局が選ぶ「Word of the Year」という流行語大賞のようなものがあるんですけど、去年は「ブレインロット」という言葉が選出されたんです。直訳すると「脳の腐敗」「脳腐れ」。アルゴリズムによって与えられる情報をぼ~っと追いかけていると、脳が腐るということを言い表しているんです。
アルゴリズムによって与えられる、好きなことや興味のある情報ばかりを見つづけるのは、ある意味、主体性を手放していること。そこから抜け出すためには、関連やおすすめに出てくる情報だけを追わないことも大事ではないでしょうか。少し意識すれば、今日からでもできますよね。
そして、考えたこともないような意見に触れられる記事を読んだり、アルゴリズムでは絶対つながらない人の話を聞いたりしてみることも大事です。その行動自体がエンパシー。エンパシーは他者の視点を獲得することでもあるので、アルゴリズムを抜け出すことが自分の世界を広げることにもつながると思います。
取材・文/宮浦彰子