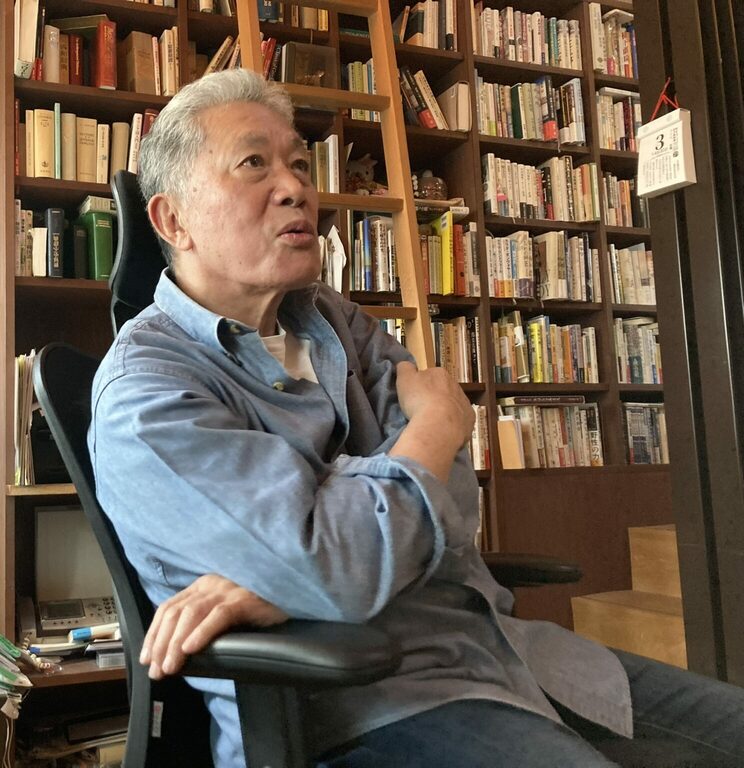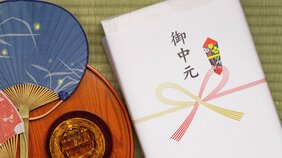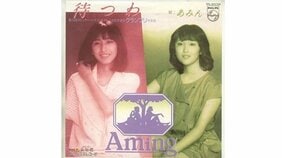「あなたの感想ですよね」はモダニズムの劣化版
内田 僕がレヴィナス論を書いた時に、フランスのある女性批評家がレヴィナスを「セクシストだ」と切り捨てたことがありました。男性が主語であることを自明としている哲学だから読むに値しないというのです。でも、たしかにその指摘には当たっている点もあるわけです。でも、レヴィナスのテクストは他にも豊かな読み筋がいっぱいあるわけです。
それを「レヴィナスはセクシストだから読むに値しない」と一刀両断してしまう。それは対象を「最低の鞍部」で乗り越えることであって、読みとしては生産的ではないと思うんです。
そもそも完璧な人なんていないわけであって、みんな信仰があったり、性的な歪みがあったり、政治的な偏見があったりする。誰だって「それぞれの歪み」を抱えているわけであって、何一つ歪みや偏りのない哲学者なんてこの世にいないわけです。
レヴィナスは敬虔なユダヤ教徒で、ヘテロセクシュアルで、イスラエルを支持していました。そのどれかをとらえて「レヴィナスは読むに値しない」と決めつけることは、できないことではないけれど、僕は「もったいない」と思うんです。一つでも欠点があると、「言説全体が無意味だ」という決めつけはしない方がいいと思うんです。
百歩譲って「レヴィナスはセクシストである」という批判はあっていいと思う。そこからレヴィナスのこれまで難解とされていたフレーズの意味が明らかになるというような読みなら。でも、この批評家はレヴィナスの読みを豊かにする気はなかったんです。
せっかく読むなら、その人の一番いいところ、その人以外誰も語らなかったような知見は何かに焦点を合わせるのが、研究者としては生産的だと思うんです。欠点を一つ見つけると、それで鬼の首でも取ったようになるというのは、よろしくないです。
李 その態度には「ためらい」がないですよね。今回の『テクノ専制とコモンへの道 民主主義の未来をひらく多元技術PLURALITYとは?』で、「テクノ専制をどうやって克服するか」と考えた場合に、もちろんテクノロジーの導入とか、関連法案の実現も必須ですけど、個人の問題として「ためらい」をどう実践すればよいのかと。
今のSNSって分断を生んで利益を上げているので、端的に気に障るじゃないですか。自分たちの意見とか考え方とかあるいは生活というものが、ビッグデータの一部として、アメリカのスーパーエリートたちが金を稼ぐために使われている。
日常での「ためらい」の実践において、個人の心持ちでも教育でもよいのですが、どういうヒントがあるのかなと。
内田 なんなんでしょうね。僕は「程度の差」というのをもっと大事にした方がいいと言っているんですけれど、それかな。「五十歩百歩」と言いますけれど、五十歩と百歩の間には五十歩の違いがある。その五十歩の違いが場合によっては生死をわかつことだってある。
うちのゼミの卒業生で小学4年生の男の子がいる人が僕のところに相談に来たんです。息子さんが学校で自分の意見を言ったら、友だちに「それはあなた個人の感想でしょう」と言われて「論破」されたそうです。それが悔しくて夜も眠れない。一生懸命ネットで調べて、言い返す言葉を探したけれど、適当なものが見つからなかった。だから先生に伺いに来ました、と(笑)。
「それはあなた個人の感想でしょう」というのはポストモダニズムのロジックの劣化した形だと思います。ポストモダニズムの功績は、僕たちが見ている世界の像はどれも主観的なバイアスがかかって歪んでいるのだから、自分に見えているものの客観性を過大評価しないようにしようという知的節度を教えたことだと思います。これは立派な貢献だったと思います。
でも、その劣化した形というものがある。それは「誰もが主観的バイアスのかかった世界像を見ている。誰一人客観的現実を知らない。だったら、すべての世界像は等価だということになる」という結論に飛びついたことです。
すべての世界像が等価なら、ひとりひとりが「自分にとって一番都合の良い世界像」を選んで、そこに安住すればいいということになる。「オレは自分に都合のいい世界観を採用するから、お前もそうすればいいじゃないか」というのが「個人の感想でしょ」という言い分なんです。
たしかに誰も100%客観的な現実を見ているわけではない。でも、そこには「程度の差」というものがあるわけですね。主観的バイアスを補正しながら正確に現実を見ようとしている人と完全な妄想の中に安らいでいる人の間には決定的な「程度の差」があると僕は思います。
たとえば、現代の宇宙科学の成果として示された宇宙観と、世界は蛇と亀と象の上に乗っかっているという古代インドの宇宙観の間にはやはり「程度の差」がある。たしかに現代の科学を以てしても、宇宙の果てに何があるか、宇宙の起源は何かという根源的な問いには答えることができません。137億年前にビッグバンがあったことまではわかった。
でも、その前には何があったのかはわからない。でも、だからと言って「誰一人宇宙についての真理を語っていないから、すべての宇宙観は等価である」ということはできません。現代の科学者に向かって「あなたの宇宙観はあなた個人の感想でしょう」と言って、だから「蛇と亀からできている宇宙観と等格だ」と言う人はいないと思うんです。そこには天と地ほどの程度の差がある。
たしかに僕たちは「主観的な知見」を語っているわけだけれども、それぞれの言明の間には、蓋然性や厳密性において程度の差がある。この「程度の差をきちんと見極める」ことが本来の知性の働きだと僕は思うんです。
あらゆる言明を程度の差を無視して「個人の感想でしょう」と言って話を済ませる奴のことを昔は「糞味噌(くそみそ)」と言いました。糞も味噌も茶色でねばねばしているから似たようなものだと言う人間に対して、いやそこには決定的な違いがあるよと教えるのが知性の働きなんです。
だから、その小4の子に、今度そう言われたら「お前みたいな奴のことを“糞味噌”というんだ」と言い返してやりなさいと伝言しました。どういう意味かと聞かれたら「家に帰って辞書引け」と言ってやれ、と(笑)。
李 「個人の感想」と言いますけど、もし感想ではない「普遍的な誰にでも当てはまる真理」があったら、人と人ってコミュニケーションを取らないじゃないですか。個人の感想だから言うのであって。もし本当に「これは絶対間違ってない」という原理があったら……
内田 人に同意を求める必要さえないですから。
李 ないですね。もちろんエビデンスは重要ですが、コミュニケーションを拒絶すると、意見をすり合わせる機会が失われてしまいます。