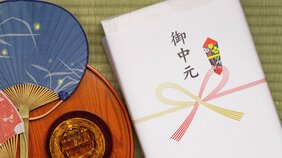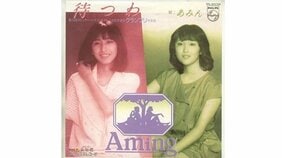「N国信者は全部バカ」なのか?
内田 一人ひとりが「主観的な知見」を語り、それが不完全なことを認め合う。そして不完全な知見を集めて、すり合わせて、そこで合意形成がなされる。対話して、それぞれが自分の考え方を少しずつ修正して、より包括的なものに拡大してゆく。それが「コミュニケーションのプラットフォームを作っていく」ことの意味だと思うんです。
李 いまのコミュニケーションのあり方を見ていると、まず現実のコミュニケーションがあって、それがSNSでも繰り広げられるという順番ではなくて、SNSのコミュニケーションがまずあって、それが現実に投射されている時代だと思います。
内田 そうですね。そう思います。SNSのコミュニケーションは「真偽・善悪」の二元論の世界なんですよね。「正しい私たち」と「間違ったことを言っているバカたち」という二元論をどちらも採用していて、その中間がない。
例えば、N国党の立花孝志の政治活動は多くの被害をもたらしたわけですから、法的にきびしく規制しなければいけないことは間違いない。けれども、それでも彼を信じるN国信者たちというのはいるわけです。この人たちがどうしてそんな歪んだ政治思想を持つに至ったのか、その経緯はわかりませんけれど、たぶんそれぞれに深い屈託や痛みを抱えていて、そういうイデオロギーにしがみつかずにはいられないという個人的事情があってのことだと思うんです。
でも、その人たちを「バカ」とひとくくりにして、「真偽善悪」の二元論の中に落とし込んではいけないと思うんですね。それはむしろリスクを高めることになるから。
フェミニズム論争の繰り返しになりますけど、もしN国信者であれ(兵庫県知事の)斎藤元彦信者であれ、政治的に完敗しても、その人たちの抱えていた心理的屈託は消えないわけです。むしろ、抑圧されてもっとシリアスなものになるリスクがある。その抑圧されたルサンチマンはしばしば別の時に別のところで、症状として回帰してくる。僕はそれを恐れるのです。ルサンチマンは怪物を生み出すことがある。だから、あまり手ひどく人を打ち負かさない方がいい。
僕は論争って一切しないことにしているんです。論争して自分が負けたらもちろん気分が悪いし、仮に僕が論争に勝ったとしても、少しもよいことはないんです。論破された相手は深い心理的な傷を負うわけですよね。その屈辱感や敗北感のせいで、その人がこれからあと生み出したかもしれない数々の知的なアウトカムの生成を僕が妨害したかも知れない。
それに、僕が後になって「あの時の考えは間違っていた」と気づいた時に、「ごめんね」と言ってももう遅い。もう向こうは取り返しがつかない仕方で傷ついてしまっているんですから。
何より危険なのは、論破すると、それが勝者にとっての「成功体験」になってしまう。人間は成功体験をなかなか手放せない。一度勝つと、以後も同じパターンで勝ち続けようとする。武道ではそれを「居着く」と言います。「勝ちに居着く」ということがあります。勝ったせいでそれ以上成長できなくなるリスクを勝者は抱え込む。
論争は勝った方にも負けた方にも傷を残す。だったら「やらない」に越したことはないというのが僕の考えです。
李 SNS上でフェミニズムが、僕の知っている範囲ですけど、若い人に受けが悪いのは、「あいつらはバカ、自分たちは真理を知っている」みたいに線を引いてしまうことが原因のひとつだと思います。それをやってしまうと、もしかしたらフェミニズムに興味を持ってくれたかもしれない外野の人たちまで引いてしまう。非常にもったいないことだと思います。
いまのSNSでの男女の対立って、「女はこうだからバカ」「男はこうだからバカ」と苛烈で、同時に単純化されたものですが、女性蔑視をしている男性のアカウントを見ると、仕事でしんどかったり、生きづらさを抱えていたり。男性嫌悪のツイートしている女性も、過去に性被害を受けていたりとか、深掘りしていくと双方にいろいろな事情があるんです。ここに実はつながるポイントもある。
今回僕が本の中に書いたテクノロジーとか実践というのは、その「つながれる部分をいかに可視化するか」という試みなので、日本でも実装していけたらなと思うんです。