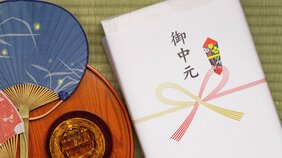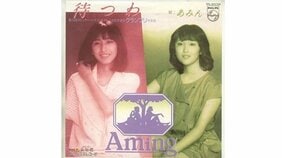SNSで「フェミ化」するフェミニズム
内田 僕が若い頃、李さんぐらいの時って、反ユダヤ主義の研究をやっていて、イスラエル文化研究会という学会に所属していたんですけれども、その時にアマチュアのユダヤ専門家というのが結構いることを知りました。ふつうのサラリーマンが「世界を支配するユダヤの陰謀」について研究をして、必死になって自費出版で本を出していたりするんです。
本人は救国の情熱に駆られて書いているつもりなんでしょうけれど、この人たちの書き物は全く読むに値しないんです。それは「自分の仮説を検証して、反証事例があれば、書き換える」という努力を一切しないからなんです。対話の場に自説を差し出して、オープンな議論に差し出す気がない。彼らは「真実」を語っているわけですから対話の必要を感じない。ただ、「教化・啓蒙」しているだけなんです。
李 今のお話を聞いて思い出したんですけど、たしかにネットとかを見ていると、韓国のことを嫌いな人ってめっちゃ韓国のことに詳しいんです。僕も知らなかった、「へえそうなんだ」ということまで調べ上げていて。
内田 そうですね(笑)。「韓国の悪い所」というタグをつけて情報をかき集めて、それで膨大なデータベースを作ってゆく。「こんな事例もある、こんな事例もある、どうだ、韓国って悪い国だろう?」と。
結論がもう決まっていて、その説に合致する事例だけを蒐集している。こういう人は当該の論件についてどれほど膨大な知識を持っていても、自説を書き換えるための可能性のドアが開いていない。僕は反証に対して開かれていないものは基本的に知的態度としては認めないんです。
李 ウォールストリートジャーナルに載っていた話で、アメリカのMAGA、トランプを支持している右派たちが、第二次大戦時の共産主義者、アントニオ・グラムシに大きな影響を受けているといいます。
それと並行して最近、ポストクリティークといって、文化批判に対する反省が進んでいます。かつてのニーチェとかフーコーのような「言説に潜む権力性を暴く」試み、たとえば夏目漱石のような古典の作品に潜む「男性中心主義」を見抜くみたいな批判理論が、今は力を失っている。トランプのような人が大統領になったら、もはや男性中心主義は潜んでいないわけで。
内田 潜んでいるどころか、男性中心主義が支配的なイデオロギーになってしまいました。
李 ですので、今までみたいな批判理論が通用しなくなっている。同時にSNS上では「正義」の問題があって、前回おっしゃっていたような「正しさを振り回して、何でも切って捨てていく」言説が目立ちます。今、大学教員をやっていて思うのは、女性も含めて学生にフェミニズムの受けが悪いんですよ。「フェミ」と蔑称的に呼ばれている。
たぶんSNS上の、悪い感じにデコレーションされたものを受容しているだけだと思うんですけど、フェミニズムといえば「なにかと文句をつけてくる人たち」みたいに思われている。萌え絵のようなコンテンツがあったら、「それは性的に搾取している」とかのケチをつけてくる連中みたいに思っている。これは非常にまずいことです。
僕も男女平等はもちろん支持しているので、たとえばフェミニズムのような文化を語る方法を、今もう一度考え直すべきではないかと思っています。内田先生は『ためらいの倫理学』(角川文庫所収)の時点でそれを実践なさっていたので、どうしてそれが可能になったのだろうか?と。
内田 そうか、フェミニズムは今の学生たちには不評なんですか……。文句を言う人だと思われているんだ。