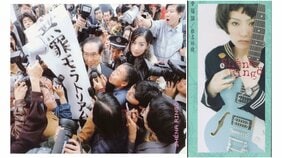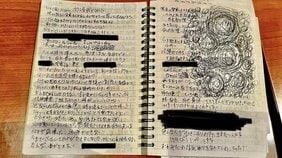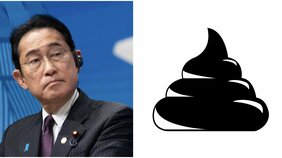居酒屋需要は2019年比で8割に満たず
日本フードサービス協会によると、2024年のパブレストラン・居酒屋の売上高は前年比105.5%だった(「JF外食産業市場動向調査」)。堅調に回復しているように見えるが、この数字を2019年との比較で計算し直すと75.1%となる。飲食需要がコロナ禍から回復しても、居酒屋の売上はいまだ8割にも達していないのだ。
しかも、牛肉や野菜などの食材費は高騰。アルバイトの時給も上がり続けている。「TOWN WORK」を運営するジョブズリサーチセンターの調査によると、2024年12月の三大都市圏の平均時給は1219円。2019年12月は1089円だった。
つまり売上が回復しないうえに、インフレで食材費や店舗運営費の負担は重くなっているのだ。そこにコロナ支援策の縮小・終了が加わってゼロゼロ融資の返済が開始。キャッシュフローが回らなくなる事業者が続出しているというわけだ。
しかし、資本力がある上場企業の稼ぐ力は戻り始めている。特に客単価が低い店舗や専門店を運営する企業の好調ぶりが目立つ。