――DINO-A-LIVEの構想はどのようにして生まれたのでしょうか。
NHKを退職後、学生時代から熱中していたバンド活動を精力的に行っていたのですが、バンド1本で食べていくことは難しく、鉄工所でアルバイトをしたり、デパートのショーウィンドウの背景を手掛けたり、博物館で造形や壁画の制作を請け負ったりしていました。
いろいろなアートの現場に顔を出す中であるとき、博物館での企画展の展示を担当させてもらうことになったのですが、当時は「企画展」というコンテンツに人気がなくて、お客さんが全然来てくれなかったんです。
自然科学に興味を持ってもらうために博物館が存在していて、その魅力を伝えるために学芸員の方々も一生懸命取り組んでおられたので、「どうすれば企画展に人が来るのか」を毎日考えました。その中で、「博物館で人気のコンテンツは何だ?」「“恐竜”だろう」と。
ちょうどそのころ、原宿・国立代々木競技場オリンピックプラザ特設会場で「ジュラシックパークインスティテュート」という映画で実際に使われた恐竜のフィギュアやロボットの恐竜等を展示するイベントが開かれていたのですが、僕の中で何かが物足りなくて。ふと「もし博物館にいるようなリアルな恐竜が歩き出したら人気が出るだろうな」と思ったんですよね。これが2003年ごろのことで、DINO-A-LIVEの始まりです。

――最初に作った恐竜は何だったのでしょうか。
アロサウルスです。僕はもともと恐竜マニアではないんですが、骨や骨格を見るのは好きだったので、アロサウルスは骨格を見たときにすごくきれいで恐竜らしい体をしているなと感じて、1号に選びました。
――完成まではどのくらいかかりましたか。
仕事の合間にコツコツ取り組む形だったので、約3年かかりました。最初から「人間の動きを恐竜の動きに変換する」ということを考えていたので、恐竜の中に人が入り、メカを使って表現するという構想だったのですが、このとき役に立ったのが、鉄工所でのアルバイト経験です。
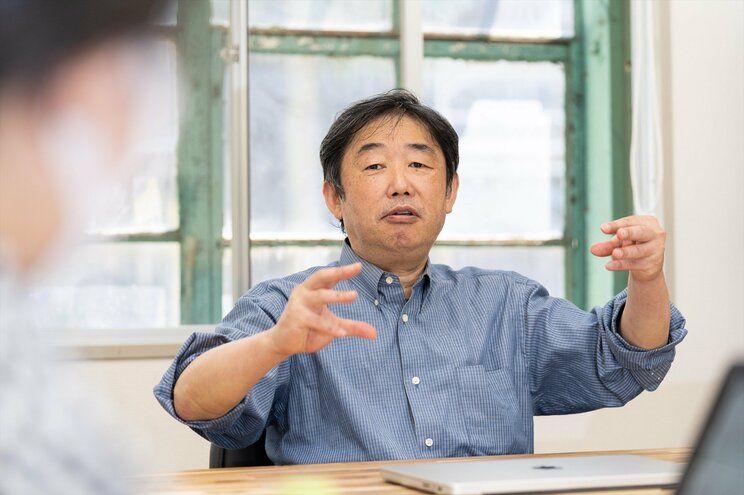
美術を専門的に学んできたこともあって、恐竜の外装を作るのはそこまで大変ではなかったのですが、内部のメカに関しても自分で一から設計図を書いて、金属を削りだして組み合わせて溶接して――ということを繰り返しました。昔から美術とメカと生物が好きだったので、自動整備の本などをよく読んでおり、エンジンがどうだとか、サスペンションがどうだとか、とにかく“中身”が好きなこともあり、熱中しました。
当時は所沢の旧鉄工所を借りて恐竜制作に取り組んでいたのですが、極寒の中、新年を迎える瞬間に旋盤の機械を回していたこともあります。除夜の鐘が鳴って、旋盤の機械音が響いて――大変でしたがすごくいい思い出です。

――プロジェクトに取り組む中で壁にぶつかったとき、どのように乗り越えましたか。
いろいろありましたが、僕自身が壁を楽観的にとらえるタイプなんですよね。「できる」と思って始めて、できなくてえらい目に合うんですが(笑)。ただ「最終的にはできるだろう」と思うんですよね。

とにかく「できない」とは思わないので、ものすごい困難があったとしても折れないというのが良いところなのかもしれません。「諦めない。折れない。できないと思わない」。これに尽きます。























