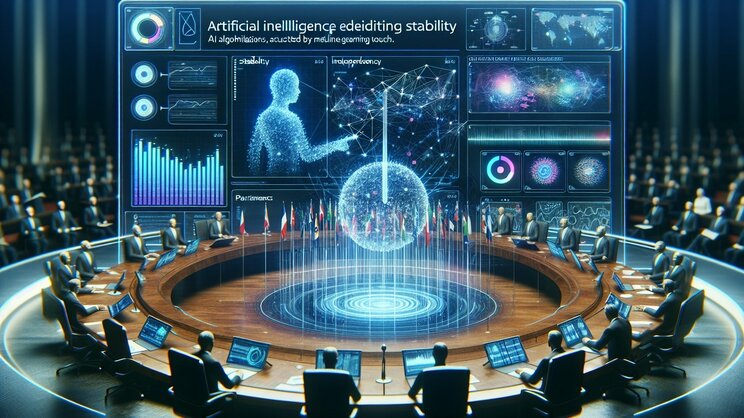緊急事態の特別権限が、平時移行後も大部分が制度に残存
具体例として、フランクリン・ルーズベルトによるニューディール政策(1930年代の大恐慌対応)、トルーマン時代の冷戦突入(1940–50年代)、9.11後の対テロ戦争(PATRIOT Actなど)において緊急事態ゆえに付与された大統領・行政機構の特別権限(規制強化、歳出拡大、監視権限など)が、平時移行後も大部分が制度に残存し、行政権力の恒久的な肥大化を招いたことが指摘されている。
たとえば、Miller Center(2025)の分析では、各大統領の単独行動がラチェット効果を生み、前政権より低い閾値で権限行使が可能になり、制度信頼の危機を招いていると論じている。
また、Mises Institute(2023)では、9.11対応のPATRIOT Actが20年以上経過してもプライバシー侵害的な権限を残存させ、自由の侵食を恒久化している典型例として挙げられている。
テクノロジーを駆使した「親切で効率的な政府」
このラチェット効果は、危機後の「再縮小」が不完全になる理由として、官僚機構の自己保存論理、イデオロギーの残渣、政治的利害関係を挙げており、チームみらいのような「状況に応じて伸縮する政府」提案に対しても、危機を口実に権限が恒久化するリスクを強く示唆する実証的知見となっている。
チームみらいが一部の人々から違和感や嫌悪感を抱かれる理由は、彼らが目指す「政府と国民の関係性」が、自由を重んじる人々の理想と根本的に異なっている部分があるからだ。
彼らが描くのは、テクノロジーを駆使した「親切で効率的な政府」だが、その前提には、政府が国民を導き、調整するという強い介入の意志がある。
政治の役割は、人々を管理することではなく、一人ひとりが自らの意志で、自由に、そして誇りを持って生きられる場を守ることにある。チームみらいという存在は、私たちに「どのような社会に住みたいのか」という重要な問いを投げかけている。
SNSでの反発は、近代社会が守り続けてきた「自立」という価値観が、新しい技術による管理とどう向き合っていくべきかという、切実な悩みの表れでもあるのだ。
文/小倉健一 写真/shutterstock