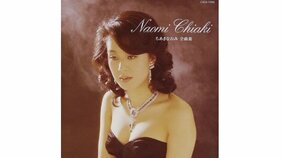「石ころを投げているシーンだけが報道される」非暴力の抵抗が「暴動」と見なされる歯がゆさ
――発信を続ける中で、情報がうまく伝わらないもどかしさを感じることはありましたか。
ありました。日本の報道番組で、デモが「暴動」として扱われるようになっていったことです。非暴力の平和なデモを続けていた市民たちは、1ヶ月ほどたつと、軍に銃で撃たれ殺されるようになりました。その際、実弾で弾圧されている市民が、抵抗のために石ころを投げ返すことがあるのですが、その石を投げているシーンだけが切り取られて報道で使われたりするのです。
それは本当にわずかな抵抗なのに、あたかも市民が暴動を起こしているかのように伝わってしまうのが、すごく歯がゆくて。彼らがあんな状況でも必死で非暴力を貫こうとしているということを分かってほしかったのです。
――西方さんご自身もSNSでミャンマー国内の現状を発信され続けましたが、ミャンマーでは、SNSはどのような役割を果たしていたのでしょうか。
クーデター後のミャンマーにおいて、SNSは世論を形成する役割を果たしていたと思います。アウンサンスーチーさんのようなリーダーたちが拘束され、民間メディアも報道ライセンスを剥奪されて、「こうしよう」と道筋を示せる人がどこにもいない中で、人々はSNS、主にFacebookで膨大な数の意見や感情を交換していきました。
その中で、無名の人たちが全体で合意形成をしていき、なんとなく一つの方向に世論が作られていく。意図せずしてFacebookがそういうプラットフォームになっていました。
「頑張れと思ってしまう自分に抵抗があった」非暴力から武装闘争への葛藤
――当初、人々は非暴力を貫いていました。それがなぜ、武装闘争へと変化していったのでしょうか。
人々が非暴力という手段を選んだのは、過去の経験から、暴力を使えばそれを圧倒的に上回る力で弾圧されることを学んでいたからです。ミャンマーでは、かつて50年以上も続いた軍事独裁下でも何度か民主化運動が起きているのですが、その際に市民が少しでも暴力的な行動をとると、軍はそれを凄惨に弾圧し、大勢の人を殺害してきました。だから、殺されないための戦略として、非暴力を選んでいたという側面がまずあります。
しかし、人々が非暴力を貫いていても、国軍は実弾で、しかも頭部を狙って攻撃するようになりました。そこで、人々は思い知るんです。軍に丸腰で立ち向かっても、殺されるだけだ、と。仲間たちがどんどん死んでいく中で、選択肢は「未来を諦めるか、武器をとって戦うか」しかなくなっていき、そして人々は戦うことを選んだのです。
――その変化を、西方さんはどのように受け止めていましたか。
クーデター以降、私はずっと「こんな不当な権力に、なぜ従わなければいけないのか」という気持ちが強くありました。ですから、武器を取るという人が出てきた時、「頑張れ」という気持ちが湧いてきたんです。
そのことに、自分でもすごくびっくりしました。私自身、国際協力の仕事でミャンマーの人々の命を助けるために働いていたつもりだったので、人の命を奪う「戦争」に対して「頑張れ」と思ってしまうことに戸惑ったんです。戦争にはもちろん反対です。今でも戦争は憎い。ない方が絶対にいい。だけど一方で、私はこの人たちに共感できてしまう。「頑張ってほしい」と思ってしまう。その葛藤は、今もあります。
――著書の中では、兵士や警官にも家族がいて日常がある、という描写も印象的でした。
ああいう時って、相手のことを100%敵だと思わないと、気持ちが戦う態勢にならないんです。私は武器を持って戦っているわけではありませんが、民主化運動を支援していたので、相手も人間だよね、という気持ちを持つことを本能的に拒否していました。
だけど、やっぱり兵士も人間なんです。たとえば街なかで軍の検問に引っかかると、荷物を開けて中身をチェックされるのですが、あるとき検問していた若い兵士は、私のカバンの中をチェックするそぶりだけして、「行っていいよ。またね」と優しく声をかけてくれたんです。そういう姿を見ると、「そんな人間らしい姿を見せないでくれ」と思いましたね。相手が悪人として存在してくれた方が、精神的には楽だからです。