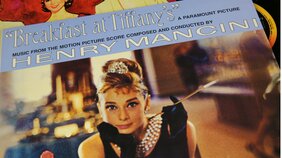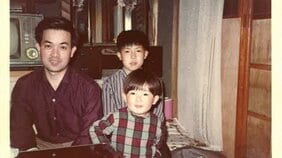教養・カルチャー
会員限定記事
「1人の女子生徒が突然、バッタリと倒れた」誰も助けようとしなかった甲子園の開会式…日本人の多くが「何もしないほうが得」と考えている危険
2017年の甲子園・夏の高校野球選手権の開会式の最中、プラカードを持つ女子生徒が倒れた。だが周りにいる球児たちは誰も助けようとしなかった。「列を崩してもいいのか?」「テレビ中継もされているし、ものすごく目立ってしまうかもしれない」彼らは判断に迷って動けなかったのであろう。では自分なら即座に助けに行けただろうか?
書籍『日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったのか』より一部を抜粋・再構成し、個人が短絡的なメリット重視するあまり、共同体が機能不全に陥ってしまう現状を明らかにする。
日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったのか #4
この記事は会員限定記事(無料) です
続きを読むには会員登録(集英社ID)が必要です。ご登録(無料) いただくと、会員限定サービスをご利用いただけます。
次のページ
共同体の「空洞化」
関連記事
会員限定記事(無料)
-
-
「1人の女子生徒が突然、バッタリと倒れた」誰も助けようとしなかった甲子園の開会式…日本人の多くが「何もしないほうが得」と考えている危険日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったのか #4
-
-
-
-
「伝統」という言葉では逃げきれないパワハラ問題…宝塚歌劇団と相撲界にみる制度に埋め込まれた理不尽日本型組織のドミノ崩壊はなぜ始まったのか #3