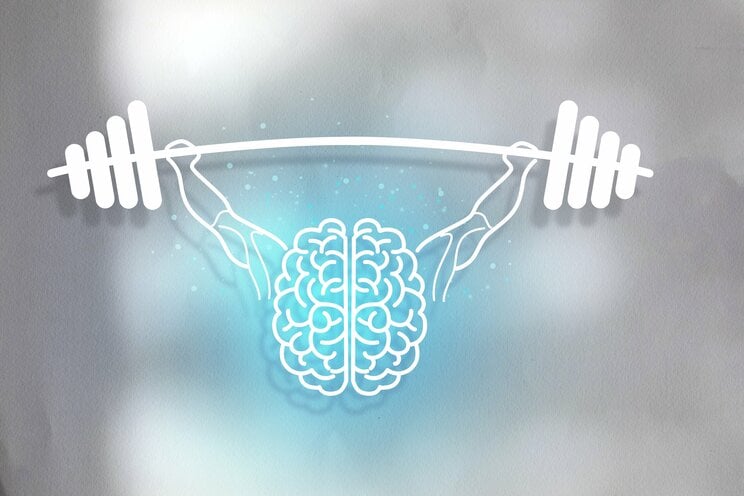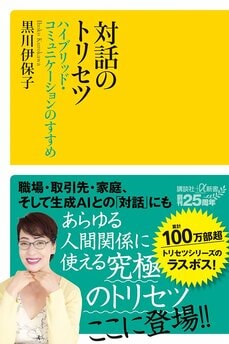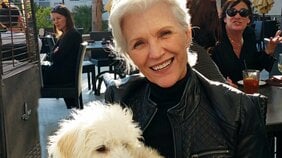無駄話が脳を活性化させる仕組み
そこで木村さんは、麹町チームの少年たちに野球を遊んでもらうために、無駄話を推奨したのである。練習の中に、中学生男子ならではの、ちょっとしたくだらないふざけ合いをする「じゃれタイム」を導入。監督に頼んで、練習の前に自然に交わされる無駄話も、あえて止めないようにしたという。無駄話やダラダラすることを許さない日本のスポーツ指導の現場でこれ、画期的すぎる。
「それが不思議なことに」と木村さんは首を傾げた。「じゃれタイムを導入してから、試合中の、短い真剣なことばの掛け合いが格段に増えたんです。僕が許したのは、無駄話なのに」
いやいや、これ、脳の機能性からいえば、ちっとも不思議じゃない。むしろ、ごく自然なこと! 私は、嬉しくて大笑いしながら、木村さんに解説をした。
グラウンドに出て、いつも気持ちよくことばを交わす仲間の中に入っていく。そんなとき、脳は、無意識のうちに記憶領域をふんわりとサーチしている。そして、ほんのわずかな情動や五感から入ってくる情報をきっかけに、あるイメージを釣り上げる。それをことばに変換し、さらに筋肉運動に換えて発音するのである。①ふんわりサーチ、②イメージ・キャッチアップ、③ことば化、④発声――この4つの演算をすばやく連携させて、「なんでもない話」をする。そう、なんでもない話って、めちゃくちゃ頭を使っているのだ。
このうち①と②は大脳右半球すなわち右脳が、③は左脳が、④のことばの発声は小脳が制御している。つまり脳全体に神経信号がいきわたり、活性化してるってこと。「なんでもない話」が脳にとって、非常に有効なエクササイズである所以だ。
また、①から③は勘の通り道。これを、毎日繰り返しているのだから、当然、勘がよくなるわけ。さらに④の小脳は、身体制御の司令塔である。勘を「発声する」という身体制御につなげることもできるけど、「手足を動かす」という身体制御につなげることもできる。つまり、ことばがすばやく出るようになった以上、手足もすばやく出ているはず。子どもたちは、声の掛け合いだけじゃなく、野球のテクニックそのものも上がったのである。
風前の灯だったこのチーム、麹町ヒーローズ(KOJIMACHI HEROES)は再建開始からわずか2年半の2024年夏、なんと東京都大会(東都少年軟式野球大会)で優勝したのである。1名だった部員は60名になり、圧倒的な強さで、その夏を駆け抜けたという。
もちろん、指導者や保護者による、そのほかの尽力もたくさんあったと思う。子どもたちの豊かな感性と、たくましくも瑞々しい生きる力と、圧倒的な努力も! けど、その思いを疲弊させず、ヒーローズ・ロードに導いたのは、やっぱり木村さんが思い描いた「楽しい野球」、じゃれタイムだったと思う。
無駄話が脳にとって、どれだけ大事か、わかっていただけたと思う。
文/黒川伊保子