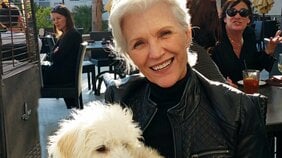無駄話が起こした奇跡
そして実は、なんでもない話こそ、脳にとって、あまりにも素晴らしいエクササイズなのだ。そのおかげで、野球少年たちに起きた奇跡を聞いてほしい。
2022年の春、東京は千代田区麹町の少年野球チームが廃部の危機にあった。メンバーが最後の一人となり、その子の中学卒業に伴い、60年の歴史に幕を下ろそうとしていたのである。胸を痛めた支援者が、スポーツ指導のスペシャリスト木村匡宏(まさひろ)さんに要請して、彼の後方支援によるチームの再建が始まった。
木村さんは、慶應義塾大学SFC研究所や、子どもの発達科学研究所の研究員も務め、プロスポーツ選手の指導にもあたっている。私は木村さんと、時折、脳と身体の関係性についてディスカッションさせていただいていて、その折に、この話を聞かせてもらった。
バックボス就任にあたって、木村さんの脳裏に浮かんだのは、夏休みにシアトルから木村さんのところに野球留学しにくる少年のことだったという。木村さんは、その子の親御さんから「アメリカの子どもたちは、どうやって野球を始めていくか」を聞き、かの国では、まずもって大人たちがおおらかで、子どもの発達についてよく理解していることを痛感した。アメリカの少年野球チームの多くは、4~6歳の幼児のときに、グラウンドで好きな遊びをすることから始まる。グラウンドで土遊びをし、ボールとじゃれているうちに、野球と出逢うのだという。
私も、その話を聞いて、歓声をあげてしまった。前にも書いたが、陸上の為末大さんがおっしゃった「対象に、遊びで出逢って、遊び心を忘れないこと。それが熟達(超一流)への道」を地で行く野球への導入である。
その成果は、子どもたちの伸びやかさに現れる。アメリカの子どもたちは、三振しても飄々とベンチに帰ってきて、楽しそうに「あのピッチャー、すげえぞ!」なんて言うのだそう。かえりみて日本の子どもたちは、空振りしたとたんにコーチの顔をうかがって硬く緊張する。三振なんかしたら、ひどく暗い顔をしてベンチに戻ってくる。木村さんは、真摯な日本の少年たちが、野球を“遊んで”いないことが気になった。