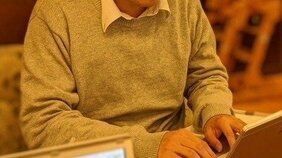まさかの「ナイター設置計画」の白紙撤回
東芝によるナイター施設の寄進に対して、真っ先に疑義を申し出たのは、恩恵を被るはずとなる東京六大学野球連盟だった。彼らの主張は「学生野球の優先、球場の品位保持に問題がある」というものだった。
彼らが訴える「品位」とは何か? 『栄光の神宮球場』には次の記述がある。
一、学生野球にナイター施設はプラスにならない。健康、学業いずれよりみるも必要が認められないばかりでなく害となる。
二、電力の基本料などのため、維持費が高くなり、そのしわ寄せが六大学の負担となる。ナイタ ー施設は物心両面よりみるも見送るべきである。
これが、専門委員により構成された小委員会の結論であった。
さらにこのとき、委員の間からは「伊丹の独断だ」とか、「東芝との汚職の疑いがある」という、根拠のない批判まで持ちあがった。
それでも、明治神宮サイドは「小委員会の結論はなんら拘束権を持たないもの」と考え、寄進契約通りに着工準備を進めていた。しかし、こうした一連の事態に対し、疑念を抱いたのが東芝本社だった。60年1月30日、東芝の平賀潤三専務が明治神宮を訪問し、「関係者全員が喜んで受けてもらえないから、白紙にしたい」と申し出たのである。
このとき、早稲田大学野球部の礎を築き、当時朝日新聞社に勤めていた飛田穂洲はこんな言葉を残している。『栄光の神宮球場』より抜粋したい。
神宮球場の大屋である明治神宮が、ナイター施設をするからといって、六大学野球連盟が反対するのはおかしい。いやなら六大学は使用しなければよい。六大学が反対するとすれば、ナイター施設のために六大学の使用料が大幅に値上げされたり、あるいは試合に支障が起こったような場合である。しかし、自分の考えとしては、六大学野球は太陽の輝くもとでやるべきであると思う。
六大学の寄付が建設費の一部に充てられて誕生した神宮球場であるが、その後の管理は明治神宮に一任されていた。戦争が終わり、接収が解除された後は、球場維持費の捻出は明治神宮に託されてきた。こうした事実を称して飛田は「神宮球場の大屋である明治神宮」と述べたのである。
当時の世論は「ナイター施設敷設」に対して好意的な反応が多かったという。ファンとしては「夜でも野球観戦が楽しめる」ということが魅力的だったからだ。
この頃の記事を見ると、マスコミ上でも擁護論が目立つ。
後に初代文化庁長官となる今日出海は「昼間は学生は学校で勉強すべきで授業にも出ずに野球をすることこそ、学生の本分にもとるものである」と強固に主張し、戦前には、東条英機内閣の内閣書記官長などを務めた星野直樹は「一千万都民のために健全な娯楽の場を増やすこと。これは今日の東京の最大の問題の一つである。その解決が一部関係者の無意味な反対のために、邪魔をされ阻止されることは許されるべきことではない」と厳しく断じている。
さらに、当時NHK会長の阿部真之助は「なぜ学生野球が昼間に限るか、どうして夜間やってはいけないか、私にはわからないのである」と述べている。さらに阿部は、神宮球場の成り立ちに言及した上で、次のように述べる。
もともとこの球場は、六大学により創設されたものだから、六大学に有力な発言権があるのはいうまでもないが、今日のごとく野球が一般化した事情の下では、六大学的立場のみで、球場の利用を考うべきでないのも、いうまでもないのである。
こうした声はあったものの、当の東芝本社が「寄進は白紙にしたい」と述べた以上、この計画は頓挫することになった。伊丹の無念は大きかった。
そして、この年の秋、後に伝説となる「早慶6連戦」が行われたのである。