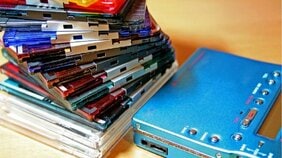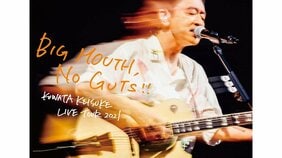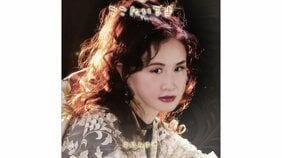ビートルズ以前にあった明治初期の洋楽ブーム
童謡や民謡によく使われるのが五音音階(1オクターブに5つの音が含まれる音階)だ。
通常のドレミファソラシドの7音から、2音抜いてある。よく知られるところだと、ヨナ抜き音階は4番目のファと7番目のシがないドレミソラの5音階。※「ドレミファソラシ」を「ヒフミヨイムナ」と読んでいたので4番目と7番目の2音を抜いて、ヨナ抜きと呼ばれている
沖縄の音楽でよく使われる琉球音階のドミファソシ。また、民謡音階(琉球音階を短調にしたもの)などで、THEBOOMの『島唄』とか、夏川りみの『涙そうそう』、森山直太朗の『夏の終わり』もそうです。
いま並べた曲からしても、日本的な音階だと思う方も多いと思うんだけど、五音音階は日本だけでなくスコットランドやアメリカの民謡(カントリー)でもよく使われている。
ギターを弾く人にはペンタトニックと言ったほうが伝わりやすいでしょうね。ペンタとは5のことです。
スコットランド民謡の『オールド・ラング・ザイン』が明治時代に日本に渡り、歌詞を日本用につけかえ『蛍の光』として歌われるようになったという有名な話がありますが、実はこの五音音階が広く日本に広まったのは明治以降だ。
私の祖父は晩年、尋常小学校の唱歌の教科書を通販で揃えて毎晩歌っていた。実は、唱歌が初めて海を渡り、大衆に広まった洋楽なのだ。
文部省(現:文部科学省)ができたのが開国後まもない明治4(1871)年、学制が頒布されたのは翌明治5年(1872)のこと。
小学校の教科に「唱歌」、つまり音楽の授業ができた。とはいえ、ずっと鎖国していたのだから、三味線や琴ならまだしも、ピアノを弾いたり楽譜を読める教師がいるわけないよねえ。
実際はどこの学校でも唱歌は行なわれなかったみたい。その後、明治8年から数年間、伊沢修二がアメリカに留学して音楽教育について学び、日本に持ち帰る。
こうして、明治14年に『小学唱歌集』ができる。でも、祖父の教材を見ても伴奏はなく、単音の形だ。和声を普及させる力がまだなく、小歌だけに限られ、洋楽の複雑な形式を理解させるところには至らなかったようだ。
とはいえこれはすごい功績で、小学校の教材やのに中学でも、女学校でも、教員の師範学校でも、市井の人々も、猫も杓子もみんな唱歌を歌うようになった。
きました唱歌ブーム‼
洋楽が全く鑑賞されていなかった明治初期に、洋楽のリズムや音階がきた日本! ビートルズより前に洋楽ブームはあったんだ。
どんだけ沸いたんだろうなあ。『蝶々』や『蛍の光』『あおげば尊し』などは姪っ子たちもいまだに歌えるのだから、明治に日本に入ってきた唱歌の功績は大きい。