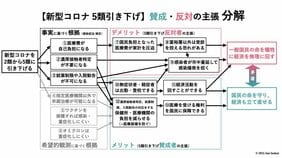「部外者」として「内側にいる」ということ
――作品の中でも少しだけ触れられていますが、広野さんはもともと、あの猪瀬直樹さんの事務所のスタッフだったとか。
2002年から、フリーライターとして独立する2015年までですね。猪瀬さんが本や雑誌にレポートや作品を書くにあたっての取材や執筆のサポートなどをする、いわゆるデータマンです。
その間、猪瀬さんは小泉純一郎政権で政治イシューとなった道路公団民営化を具体化する政府の委員を務めたり、その仕事ぶりがきっかけで東京都の副知事に任命され、のちに知事にもなった。霞が関は取材対象ですが、都庁は一時、「職場」にもなったのです。
もともと私が猪瀬事務所に入ったのは、三島由紀夫の生涯を追った『ペルソナ』、太宰治の「生」への執着を描いた『ピカレスク』といった評伝作品に感銘を受けて手紙を出したことがきっかけでしたから、思いもよらぬことばかりの歳月でした。

――読み始めてすぐ、最初にピンときた記述があります。それまで社会問題を「外部」から追及していた猪瀬さんが――2007年当時に都知事だった石原慎太郎さんの要請で――民間人として、東京都の副知事に就任することに。本書でも「戸惑い」を吐露した部分がとても心に響きました。引用させて下さい。
〈例えば道路公団改革で最大の問題は四十兆円の借金だった。借金返済だけを考えれば1キロも新規建設をしないほうがよいに決まっているが、その一方、医療へのアクセスや経済振興にかける地方の期待を軽んじることはできない。改革と恩恵を両立させようと、「建設を3割削減したらどうなるか」という試算をつくったとたん、こんどは「あの猪瀬は残り7割は建設しようとする建設推進派だ」などと批判が出て、どうしろというのだと感じて閉口した。
メディアは、行政に助言する“客観的な有識者”が“偏った政府”を指弾する構図に飢えており、そうでない姿は退屈に映る。無事やり遂げてあたりまえ、対立図式を超えて現実的な改善や改革を導き出そうとすれば、こんどは“政権におもねった”“国土交通省寄り”とレッテルを貼られるものだ。権力の助言者になることは、そんな損を引き受けることでもある。猪瀬事務所で青春をついやした先輩スタッフは、改革プロセスが終わるころには一人またひとりと事務所を去った〉(『奔流』より引用)
まさに、今回のコロナ対策に関わった専門家たちを彷彿とさせる状況です。