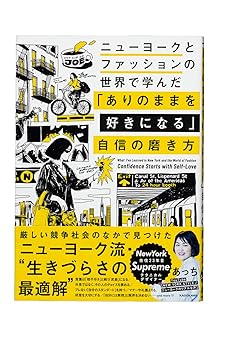米国では、大学進学にかかる学費が高額です。
州内の公立大学で、年間平均約1万1610ドル(約170万円)。私立大学では約4万3350ドル(約630万円)にも上ります。そこに仕送りも含めると、負担は大きくなります。米国では、約4300万人(学生の約4割)が、学費や生活費のために学生ローン(Student Loan)を利用しているといわれています。その総額は、1・77兆ドル(約225兆円)となっています。
ここで注意すべきは、「学生ローン」という言葉の意味が、日本と米国でニュアンスがやや異なる点です。日本では「学生ローン」というと、消費者金融などで学生が借りるローンのイメージが強く、ややネガティブな印象もあります。
対して米国でいう「学生ローン」は、大学や大学院の学費・生活費のために政府や金融機関から借りる教育ローンのこと。返済は社会人になってから行うのが一般的です。日本でいうところの、JASSO(日本学生支援機構)などから借りる「奨学金」に近いといえるでしょう。
学生ローンと奨学金……言葉は異なっても、若者が何百万円もの負債を背負って社会に出る構造は同じです。
もし、米国で学生ローンを払えなかったらどうなるのでしょうか。まず、返済が遅延すると、延滞料が発生し、さらに利子が加算されます。もっとも深刻な影響は、信用スコア(クレジットスコア)の低下です。信用スコアが下がると、住宅ローンや自動車ローンなど、他のローンの金利が高くなったり、そもそも借り入れができなくなったりします。
最悪の場合「デフォルト(債務不履行)」とみなされて、給料や税金の還付金の差し押さえが行われるなど、強制的な回収措置が取られます。
学生ローンは若者にとって、とても重い負担です。学生ローンの返済が結婚、出産、住宅購入、起業などを遅らせ、格差拡大や米国経済そのものの成長の妨げになるのでは、という見方もあります。
バイデン前大統領は、低・中所得層向けに最大2万ドルの学生ローン返済免除(Loan Forgiveness)を提案しましたが、「規模が大きすぎる」として2023年に連邦最高裁が違憲と判断し、頓挫しました。
コロナ禍では学生ローン返済が一時的に停止され、2023年まで延長されていました。その後もしばらくは、強制的な回収には踏み切っていなかったものの、トランプ政権になり、「借りたものは返すのが当たり前」という立場から、今年5月に学生ローンの回収が再び始まったのです。
これは前政権とは真逆の姿勢です。これにより多くの人が、デフォルトのリスクに直面しているといわれています。学生ローンは政策によって大きく左右されますし、これから進学する学生には、これまで以上に大きな負担が課されることになります。
時代の変化も急激です。少し前までは、「ホワイトカラーの仕事に就けば高収入が得られる」と信じられてきました。けれども今では、そうした知的労働こそAIに置き換えられやすくなり、最近の学生たちは就職すら難しくなっています。
一方で、プラマー(配管工)や電気工事、建設などのブルーカラー職はAIによる代替が難しいとして、高収入の人気職となりつつあります。
このように、時代の変化によって「正解」とされるキャリアの選択肢は大きく変わってしまいます。だからこそ大切なのは、自分が何に向いているか、何をしていると楽しいかを知ること。その軸があれば、時代がどう変わっても、自分なりの道を選ぶ力になるはずだと思います。