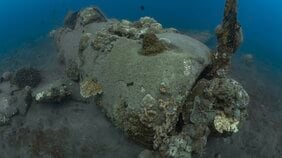「ゼロ戦」での初陣
野口の所属する第三〇六飛行隊は宮崎県の富高海軍航空基地へと転戦。来る日も来る日も特攻を想定した実戦訓練が続いた。
1945(昭和20)年3月18日。野口はこの特別な日を忘れない。
米艦隊による日本本土への空襲を阻止するための、「邀撃戦(=迎撃戦)でした」。現代でいうスクランブル発進で飛び立った、この出撃が、野口にとって初めての空中戦だった。
「ゼロ戦」操縦士となった野口の初陣である。
午前7時過ぎ。野口らが操縦する「ゼロ戦」4機が基地の滑走路から次々と離陸。編隊を組んだ4機の操縦士は一気に操縦桿を引き上げ、急上昇していく。
朝日を浴びながら、高高度を飛行中の敵戦闘機の編隊へと向かっていった。
「初めての空中戦の記憶は忘れません。1番機を操縦する隊長が、『俺に付いて来い!』と離陸直前、声をかけてくれていました。しかし、無我夢中で隊長機に付いていくのが精いっぱいで。操縦桿に付いた機銃の引き金(トリガー)の引き方も思うようにならず、気づいたら弾薬を撃ち尽くし、弾切れです。極度の緊張状態でした」
弾薬が切れると、戦闘空域からいったん離脱し降下。弾薬を補充するため、基地へと戻らねばならない。
「初陣では4回、この離着陸を繰り返しました。その度に整備員に大急ぎで弾薬と燃料を補給してもらい、空中戦へと戻っていくのです」
この日の邀撃戦での日本海軍の被害は甚大だったという。
「目の前で多くの僚機が撃ち落とされていくのを見ました」
無事に基地に帰還した野口だが、夕食を取るために向かった食堂で大きな衝撃を受ける。
この日、野口が、「同期のなかで一番仲が良かった」と語る友人の操縦する「ゼロ戦」が帰還していなかったのだ。
「神雷部隊へ志願するか?」
そう上官に聞かれた、あの日のことを野口は思い出していた。
「私には両親がいるし、長男でもない。お前もか。では一緒に行こうか……」
そう語り合いながら神雷部隊へともに行くことを決めた親友、畠山力が今日の空中戦で戦死していたのだ。
野口は、「死を最も間近で感じた瞬間だった」と言う。
「基地では上官から、よくこう言われていたんです。『部隊では友人はできるだけつくるな』と。なぜ、上官はそんなことを言うのだろうか。私たち仲間は、皆、不思議な気持ちでそう思っていましたが、その言葉の意味が、このとき、よく理解できました」
その後も、ずっとこの辛い思いが途切れることはなかった。
「毎回、出撃して基地へ帰還し、食事中に分かることがあります。そこで初めて、席についていない仲間がいることを確認するのです……」
すると野口が「仲の良かった4人で撮ったんですよ」と話しながら一枚の記念写真を取り出した。
そこには野口と同様に制服姿で椅子に腰かけた畠山が写っていた。
「前にいる畠山と私が飛行教官で、後ろに写っている2人が練習生です」
教官をしていた時代があった。そう野口が語った当時、一緒に撮った写真だった。
少し緊張した表情の4人。軍人らしく凛々しくも、全員まだどこかに幼さを残した10代の若者たちだった。
数時間に及ぶロングインタビュー中、終始、冷静沈着、理路整然と、かつ気丈に語り続けてくれた野口が、ぐっと感情を押し込めるようにして、小さく嗚咽する瞬間が何度かあった。
両眼から涙がこぼれ落ちないように、ぐっと唇を噛みしめながら……。
初陣で親友を亡くした、その日に思いを馳せた瞬間、涙をこらえきれなくなった野口の心の奥底から込み上げてくる嗚咽の声が、慟哭のように聞こえた。
その声は、今も筆者の胸に刻みつけられ、残されている。
文/戸津井 康之