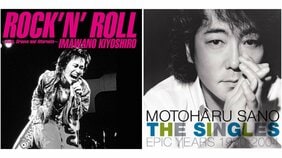反戦と平和を訴える新しい歌『一本の鉛筆』
1974年に『一本の鉛筆』という歌が誕生したのは、1945年8月6日に原子爆弾によって焦土となった広島で、復興と平和をテーマにして始まった音楽祭がきっかけだった。
美空ひばりには、幼少時に父が徴兵された後、4人の幼子を抱えた母と一緒に戦火の中をかろうじて生き延びてきたという、横浜大空襲の体験が生々しく記憶されていた。かろうじて避難した手作りの防空壕では、生き地獄のような恐怖を味わった。

戦後になってから、夏の日ざかりに焼けたアスファルトの道を、魚屋の仕入れでリヤカーを引くゴム長靴を履いた母の姿を、美空ひばりは鮮明に覚えていた。
“世界に平和を発信したい”という広島テレビ放送の企画に賛同し、音楽祭への出演を快諾した美空ひばりは、課題となった書き下ろしの作品『一本の鉛筆』に取り組んだ。
この真っ直ぐなメッセージ・ソングを作詞したのは、映画の脚本家だった松山善三である。彼は「広島平和音楽祭」の総合演出も引き受けていた。
そして黒澤明監督の映画音楽でも知られる音楽家、佐藤勝が作曲とアレンジを引き受けて、反戦と平和を訴える新しい歌が完成する。
一本の鉛筆と一枚の紙があれば、たった一人でも反戦の意志を訴えることができる……。
美空ひばりが1974年8月9日に開かれた「第1回広島平和音楽祭」の会場で、この歌を初めて人前で歌うためにスタンバイしていた時のことだった。その日も朝から、暑い1日になった。
会場の広島体育館には冷房設備が備わっていなかった。したがって出番を待つための場所として指定された体育館の用具置き場のようなスペースには、一本の氷柱が置いてあるだけだった。
そこで早くから出番を待っていた美空ひばりに、暑さを気遣った広島テレビのディレクターが思わず声をかけた。「ここは暑いですから、冷房のある別棟の楽屋でお待ちください」
美空ひばりその時、誰に言うでもなくこう呟いたという。
「あの時、広島の人たちは、もっと熱かったのでしょうね」
10月1日に『一本の鉛筆』はシングル盤として発売されたが、B面の『八月五日の夜だった』ともども、広島市へ投下された原子爆弾によって起こされた未曾有の悲劇について、怒りを込めて書いた作品だった。