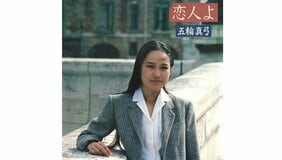幼少期から「何はなくとも家電」な生活だった
––––経済評論家である勝間さんですが、そもそも家電やガジェットに強く惹かれるようになったきっかけはなんだったのでしょうか?
勝間和代(以下同) もともと父がAV家電の下請けの仕事をしていたんですよ。だから家には部品がよく転がっていましたし、“ノルマ”みたいなものがあって最新家電を買うことも多かった。当時は下町の長屋に住んでいたのですが、父はよく「この辺りで、うちが最初に洗濯機とテレビを買ったんだぞ!」と自慢していました(笑)。
––––幼少期から最新テクノロジーが身近にある環境にいらっしゃったんですね。
そうなんです。だから今回執筆した書籍に対して「集大成だね!」と言ってくれている方もいらっしゃいます(笑)。
CDプレーヤーもかなり早い段階で持っていましたし、中学1年(1981年)のときにはすでにパソコンを所有していました。社会人になってからも、「何はなくとも家電」。なけなしのお金で乾燥機を導入したり、型落ちの家電を買ったり。ISDN(インターネット回線)を自宅に引いたときは、業者に「葛飾区で2軒目」と言われましたね。
––––新刊『勝間家電』を読むと、家電を単なる便利な道具としてではなく「自分の代わりに働いてくれる存在」として捉えていらっしゃる印象があります。勝間さんにとって、家電への投資はどんな意味を持っていますか?
仕事を辞めて自宅にいる時間が増えたとき、「もう人を雇う時代じゃないな」と思ったんです。働いていた頃は週に何度か家事代行をお願いしていましたが、家にいるなら自分でやったほうがいいな、と。
そのタイミングでホットクックや新型ルンバが登場して、「これは人を雇うより家電を雇う時代だな」と実感しました。そこから、“人を雇う”のではなく“家電を雇う”ようになったんです。
––––「自分でやって質が下がるなら、家電に任せて質を上げて時間を取り戻す」という考えですね。
そう。洗濯も皿洗いも、機械のほうがずっときれいで効率的なんです。だから「洗濯は機械でやるのに、なぜ皿は手で洗うの!?」って、周りにもよく言っています(笑)。