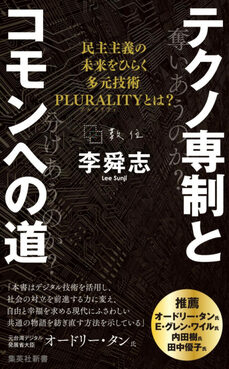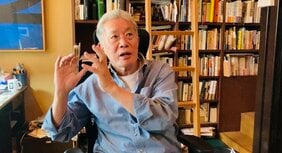ポストシンボリックコミュニケーションの限界
とはいえ、あらゆるコミュニケーションがポストシンボリックコミュニケーションに取って代わられればいい、というわけではない。そのテクノロジーは革命的であるがゆえに、致命的なリスクをはらんでもいる。
テクノロジーが労働者の監視に使われるのは未来の話ではない。現在、AmazonやUberといった企業は、処理能力の向上とトラブルの最小化のために、配達員や倉庫従業員の行動や成果を監視し、収集したデータをアルゴリズムと組み合わせることによって管理の自動化を図っている*6。
ポストシンボリックコミュニケーションのテクノロジーは、この監視をいっそう完璧なものにするだろう。心を無制限に可視化することで、思考、感情、動機を直接的に操作できてしまうのだ。
同様に、政府はポストシンボリックコミュニケーションのテクノロジーによって心の中までも監視するだろう。反政府的な態度を表明していなくとも、心の中の反政府的思考・想像すら感知できるようになってしまう。
また人間が物理的な世界とのつながりを失い、テレパシーによるコミュニケーションに過度に依存することで、伝統的なコミュニケーション技能や文化的慣習が衰退し、人々は精神的なつながりだけに頼るようになるかもしれない。
したがってポストシンボリックコミュニケーションの活用にあたっては、プライバシーや自律性の問題を考慮すると、従来のコミュニケーションとのバランスを維持しなければならないだろう。
たとえば文字によるコミュニケーションは、テレパシーほど直接的でも即時的でもないが構造化され熟考されている。送信者は考えを言葉や文章にまとめる必要があるため、即時的なテレパシー通信にはない、高い抑制と省察が得られる。コミュニケーションには遅さと間接性が必要なときもあるのだ。
また市場と投票システムも拙速さに対抗するものを提供する。市場では、消費者と生産者が下した無数の決定が価格メカニズムを通じて伝達される。この仕組みには、個人が考えや動機の全範囲を明らかにする必要がないため、意思決定のプライバシーが確保されている。
同様に、投票は、個人がある時点での意思を表現する、熟考にもとづくコミュニケーションである。テレパシーの流れとは違い、投票は解釈可能な方法で国民の意思をまとめ、個々の投票者の自主性を維持する。
このアプローチは、効率的なコミュニケーションと個人の自主性、プライバシー、民主的なプロセスの保護との間のバランスを維持する上で重要であり、それによってテレパシー的コミュニケーションの行きすぎに対する重要なチェックとして機能するだろう。
ポストシンボリックコミュニケーションは他のあらゆるコミュニケーション形態を駆逐するのではなく、それらとのバランスを維持することで、その真価を発揮することができるのだ。
脚注
*1 ジャロン・ラニアー、井口耕二訳『人間はガジェットではない IT革命の変質とヒトの尊厳に関する提言』ハヤカワ新書juice、2010年、332頁。
*2 たとえば「儀式とは、ヒトの心理プログラムのバグを巧妙かつ多様な方法で利用する『マインドハック』の集合体と考えることができる」。リズミカルな音楽に合わせることと整然と秩序正しく共通の目標に取り組むことが相乗効果を生み、連帯感や協力への意欲が強められるのだ。ジョセフ・ヘンリック、今西康子訳『WEIRD 「現代人」の奇妙な心理 経済的繁栄、民主制、個人主義の起源』上、白揚社、2023年、117-118頁。
*3 Andrea Stevenson Won, Jeremy N. Bailenson, Jaron Lanier, “Homuncular Flexibility: The Human Ability to Inhabit Nonhuman Avatars,” Robert Scott and Stephen Kosslyn (eds.), Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource, John Wiley & Sons, 2015.
*4 ジャロン・ラニアー、井口耕二訳『人間はガジェットではない IT革命の変質とヒトの尊厳に関する提言』ハヤカワ新書juice、2010年、326頁。
*5 William Steptoe, Anthony Steed, Mel Slater, “Human Tails: Ownership and Control of Extended Humanoid Avatars,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol.19(4), 2013, pp.583-590.
*6 ダロン・アセモグル&サイモン・ジョンソン、鬼澤忍・塩原通緒訳『技術革新と不平等の1000年史』下、早川書房、2023年、144-145頁。
写真/shutterstock