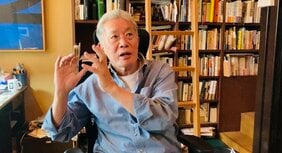老いをあらかじめ体験する
日本科学未来館の中には老いパークという体験型展示がある。この展示では、たとえば白内障の視覚を体験できたり、高音部が聞こえにくくなった聴覚を体験できたりと、老化による目・耳・運動器・脳の変化を疑似体験できる。
頭に入れたはずの買い物リストを思い出すことを周囲に邪魔され、カートによりかかりながら横断歩道を渡っていると信号が変わってしまい車にクラクションを鳴らされる。これらをシミュレートできることに加えて、老化現象が起こるメカニズムや対処法、将来身近になるかもしれないサポートテクノロジーなどを知ることができるのだ。
台湾のオードリー・タンたちは、老いパークはただの展示ではなく、時間を超えた没入型の会話だと指摘する。それは視覚、聴覚、運動機能、認知機能の変化と苦痛の感覚を通じた、高齢の自分との対話なのである。それによって、未来の自分だけでなく、高齢者とのもっと深いつながりが育まれる。
「老い」とは、誰にとっても避けられない未来でありながら、その実態を想像するのは難しい。というのも視覚や聴覚、運動器、そして脳の変化は、ごく個人的な感覚体験であり、言葉ではうまく伝わらないからだ。
老いパークでは、参加者は身体のあらゆる感覚を活用し、言葉や記号を解釈するだけでなく内的な感覚体験を通じて情報を受け取る。それは伝達することがきわめて難しい深部感覚を、言葉や記号ではない媒体でコミュニケーションするポストシンボリック(表象)コミュニケーションの具体例なのだ。
ポストシンボリックコミュニケーションとは、記号の仲介なしに、直接的に体験を共有することを指す*1。たとえば老人にネガティブな固定観念をいだいている高校生に、視点交換で老人の立場を実感できるようなシーンを再現してみせれば、固定観念を打ち砕けるかもしれない。老いパーク、ひいてはポストシンボリックコミュニケーションは、コラボレーションの深さと広さのトレードオフを改善する希望を示している。