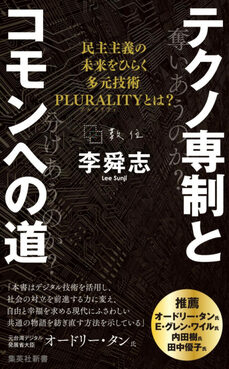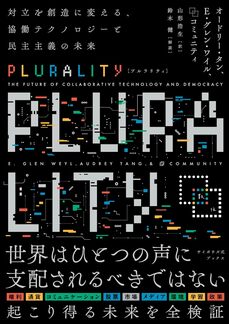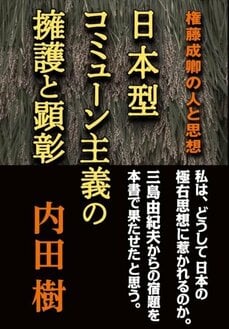人が成長できる政体は民主主義だけ。
李 これからは学校教育でもテクノロジーは導入されていくので、もう少し有効に活用できるようにしたいです。ある種の教育を公共圏に変えていくために、ひいては社会全体というか、先ほども言ったように「民主主義というのは教育の場」なので、その場を提供できるように。
現在の社会状況を語る時、僕はあまりこの言葉が好きではないんですけど、「ポピュリストに動員された愚かな連中」みたいな言い方をよく聞きます。たしかに愚かかもしれないですけど、問題なのは動員されることではなくて、一人ひとりに教育の機会、学習する機会がないことです。
「あんなつまらないやつに投票しちゃった。今度からSNSでニュースを見る時は気をつけよう」とか、そういう学びの機会がないことが問題で、僕も含めて人はみんな愚かですけど、少しずつ学んでいくことはできる。学んでいくことができる政治形態というのは、民主主義だけなので。
内田 その通りですね。民主政は市民たちが政治的に成熟していないと維持できない危うい政体なんです。帝政とか王政とかなら、民衆は自分たちが統治されていることに気づかないぐらいに政治に無関心であることが許される。許されるどころか奨励される。人々が統治に対して無関心なのが帝政や王政の理想なわけですよね。
民主主義はその正反対で、「最悪の政治形態」とチャーチルが言ったように、一定数の「まともな大人」がいないと機能しないシステムなんです。市民が成熟してくれること、賢明になってくれること、道義的にも知性的にも立派な市民になってくれることを政体そのものが要求する。この政体からの要求に市民が応えないと、民主政はたちまちイディオクラシー(愚民制)に劣化する。
民主主義はその意味では本当に危うい、脆弱な政体なんです。でも、市民に人間的成熟を求める政体というのは民主政以外に存在しないわけです。だからこそデモクラシーを守らなければならない。
マニフェストなきコモンの誕生
内田 僕の友人にモリテツヤ君という人がいて、彼は鳥取で「汽水空港」という小さなカフェと本屋をやっているんですけれど、先日町議選に立候補して当選したんです。本屋とカフェの店主は引き続きやるので、「この店にはいつ来ても町議会議員がいるから、一人ひとりの悩み事、困り事があったら言ってください」と。
それを議会に上げていって、場合によっては予算をとって、困り事を解決していきますから、と。そういう人たちって、前回の統一地方選挙からたくさん出てきているみたいです。僕の友だちでも何人か「もう我慢できない」と言って地方選に出て、けっこう当選しました。
コモンの構築って、今みんなあちこちでやっているんです。地方議会に出たり、地方で文化発信したり、経済活動したり。小さいスケールのものが、各地で同時多発的に始まっている。新聞はほとんど報道しませんけど、3・11の後から始まった流れなんです。あれからもう15年ですから、かなり大きなトレンドになってきています。みんな手づくりで一生懸命、「どうやってコモンを作って維持するか」ということを実験的にやっています。大きな変革の動きが一人ひとりの発意で起きている。この「一人ひとりの発意で」というところが貴重だと思うんです。
1970年ごろ、学園紛争が終わった後に、敗残の活動家たちが帰農するという流れがありました。その時は「これは革命闘争の継続なんだ」というようなイデオロギー的な基礎づけがあった。でも、そうなると「この活動がどこが革命的なのか」ということをうるさく査定された。
だけど今コモンを作ろうとしている人たちは、理論もないし教科書もない。旗を振るリーダーもいない。みんな友だちなんです。「自分の実践が正しくて君のは間違っている」というようなおせっかいなことを言う人はいないんです。
これが今の運動の一番いいところだという気がするんです。マニフェストがないから多様性がある。
李 そうですね。まずマニフェストがあって、それに従う集団が生まれるというよりは、いろいろな集団がマニフェストなしにつながり合っていく。
今日お話させていただいて、僕も理論をやっている人間なので、「地方におけるコモンの自治」を考える時、あまり教条的になってはいけないと思いました。多元的に、東アジアという独特の歴史と文化を持った領域を意識しつつ、テクノロジーと社会について考えていこうと思います。
たとえば今、人新世って言われるぐらい危機的な状況が世界的に起こっていて、そこで技術のことをどう考えるかというのがすごく大事なテーマで、そのいろんなアイデアの中の一つに、今言われている「テクノロジー」とか「技術」というのはいわゆる西洋的な技術観、テクノロジー観であって、それをもっと多様化していくべきなんじゃないかという議論があります。
中国の哲学者でユク・ホイさんという方がいらっしゃるんですけど、『中国における技術への問い』(邦訳、ゲンロン)という本の中で、中国の技術観を古代まで掘り下げて見ていって、そうすると天とか、道とつながっていたりとか、あるいは技術とか芸術とか政治とか自然というのが混然一体となっていたりとか。
もちろん中国の技術観が正しいんだと言いたいわけじゃなくて、批判的にも取り組んでいくし、そこには京都学派の話とかも加わってきます。現在、僕はユク・ホイさんの本を翻訳されている伊勢康平さんたちと一緒に研究会をやっていて、東アジアの技術観を、社会や文化との関係性から考察していけたらと思っています。
内田 李さんの場合は、日韓という2つの国の間をブリッジできる、ある種特権的なポジションにいると思います。「日韓の連携」ってこれから東アジアの中心的な政治課題になると僕は思っています。
この先、日米同盟基軸が破綻したら、日中同盟になるか、日韓連携か、あるいは完全に孤立するかしかないわけですよね。僕は合理的な解としては日韓連携しかないと思うんです。軍事同盟になることはないですけど、日韓連携すると、人口が1億8000万で、GDP6兆ドルで、米中に次いで世界第3位の経済圏になる。
5月にまた韓国に行って講演旅行をするんですけど(*対談は4月30日に行われた)、そこでも日韓連携のことを話してくださいと言われています。今の日本と韓国は、政府間は冷え切っているけども、経済活動は活発だし、観光客は韓国から800万人来て、日本から400万人。
活発な交流があるわけです。若い子たちはハングルを勉強しているし、K-POPを聞いているし、向こうの人たちも日本の文化に興味を持ってくれている。市民のレベルの、草の根の交流が本当に盛んなんですよね。これをだんだん広げていって、本当の形の日韓連携にしなきゃいけないと思っているんです。