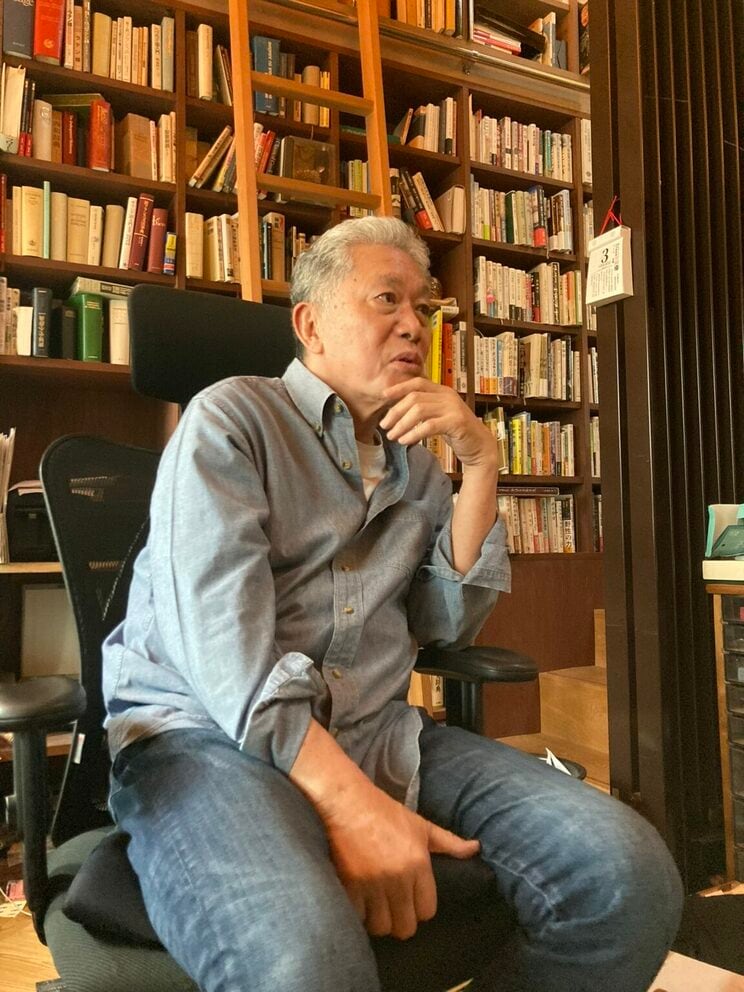愛は伝わらなくても「敬意」は伝わる
内田 集団としてのパフォーマンスを上げる、全体としての収穫を豊かなものにするには、「誰が集団の足を引っ張っているんだ?」という「犯人捜し」をするより、誰に対しても親切にするのが一番効率的なんです。
人って親切にされると、ちょっと「開く」んですよ。親切とか敬意には感染力があるんです。こちらが愛情を示しても全く気付かないという人はいるんです。でも、不思議なもので、敬意を示されて気がつかない人っていないんです。「鬼神を敬して之を遠ざく」と『論語』にありますけれど、鬼神の類でさえ、敬意を持たれていることはわかるんです。鬼神に伝わるものが人間に伝わらないはずがない。
だから、小さく固まって自分に居着いている頑なな子たちには愛を示しても通じないけれど、敬意を持って接すると「敬意を以て接している」ということだけは通じる。この人は自分に敬意を持っているということはわかる。
敬意って「距離感」のことですからね。相手は結構遠くにいて、自分の方を見ているだけです。もしここで心を許して、心を開いても、急に近づいてグサッと刺すというようなリスクはない。あんまり近間に寄らず、遠間を保ちながら、ただ見ている。そうするとちょっとずつ心が開くということがある。武道における「間合」と同じで、「適切な距離をとること」ってすごく大事なんです。
李 そう考えると、いくらインフラのテクノロジーが発達しても、教育においては、先生がおっしゃるような人間関係というものが、むしろ必要になっていくのではないかと思います。
内田 人間ってやはり生き物ですから、誰もが豊かな潜在可能性を蔵している。まだ芽が出ていなくても、きっかけさえあれば開花する。それは僕の教育者としての経験がもたらした信念なんです。可能性を持たない人は一人もいない。それが開花しないのは、周りの支援が足りないからだという気がするんです。
査定とか評価とかは、可能性を開花させる上ではほとんど意味がないと思います。それよりは、学生と向き合っている時にそこで行き交う言葉が豊かなものであるということが、一番大事だと思います。
4年間学校で過ごした後になって「大学の記憶って一つしかない」ということはよくあるんです。「あのとき先生がこう言ったその言葉が自分の転換点になった」みたいなことを後から言ってくる卒業生がよくいるんです。こっちは自分が何を言ったのか覚えていないんですけれども、向こうはその一瞬に「開いた」わけです。だから、いろんな先生がいて、いろんな授業をやって、いろんなことをつぶやくのが有効なんです。「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」で何かが誰かにヒットするかもしれない。
李 おっしゃるように、なるべくいろんな先生がいた方がいいと思います。僕も学生の頃、「生徒から大人気」みたいな先生よりは、ちょっとニヒリスティックな先生のほうが好きだったり、世の中にはいろんな大人がいるということを知ることが、受験勉強よりも学びになっていました。だから学校教育は学校教育がすべきことをやればいいし、学校教育が問題というより、「学校教育以外の教育の場が壊滅している」ことが問題で、やはり凱風館みたいなコモンが必要なのだと思います。
内田 今の教育行政の制度設計をしている人たちは、学校でいい先生に出会って、居着きから解き放たれた。おかげで人間として成長したという学校における温かい経験をたぶん持っていないんだと思います。でも、本当は学校に行ったことで自分は「開いた」という経験を持っている人こそが行政の要路に立つべきなんですけどね。
李 そうですね。ちょっと暗い話をすると、査定のテクノロジーって今すごく発達していて、教師の成果を数値化するアルゴリズムが、長足の進歩を遂げています。そのせいで目の前の生徒ではなく、「アルゴリズムの数値をどう高めるか」ということが、教える側の基準になりつつあるんです。
内田 どうやったら高まるんですか?
李 項目がありまして、生徒が全国学力調査で高得点を取ると上がるとか、クラスがいじめゼロになると上がるとか。そういう指標を常に気にして、たとえばイギリスでは、成績の悪い子は全国テストの時に欠席させる例なども報告されています。たしかにアルゴリズムの数値は上がります。本末転倒もいいところですが、そのように現場の教師を査定するテクノロジーが、次々と導入されつつあります。他にも、授業中の生徒の身体データを監視するとか。
内田 そこまで行っているんですか? 脈拍とか?
李 そうですね、脈拍とか集中力とか。血圧とか発汗とか。
内田 それで集中力がわかるんだ。身を乗り出して興奮したら血圧が上がるのかな。みんなの血圧が低い時は、「テンションの低い授業をしていますね」とか言われるのかな。やだなあ。