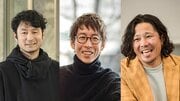野球という題材に出会ったきっかけ
早見 僕は、『嫌われた監督』を週刊誌の連載中から楽しみに読んでいたんです。個人的に、野球ノンフィクションで書き手が剝むき出しになっていないものはあまり好きではないんですが、鈴木さんの作品はもう、胸焼けするくらいご自身が表れていて毎週たまらなかったです。
鈴木 ありがとうございます。
早見 若手記者だった当時の鈴木さんが、落合博満というバケモノと対峙している場面なんて、本当に夢中になって読んでいました。
クロマツ 僕も同じくです。落合さんや星野仙一さんと邂逅する場面って、ワクワクさせられる半面、「ああ、自分だったらこんなに緊張感のある場面には居合わせたくないな」と思いながら読んでいました(笑)。
早見 鈴木さんは記者時代と比較して、ノンフィクション作家になってから、文章の書き方は変わりましたか?
鈴木 変わりましたね。やはり、文章量が圧倒的に違うので。新聞記者の時は、もっと一次情報を重視していました。僕が記者をしていた時代は、まだ「スクープ」という言葉が新聞社にも残っていて、そこで記者の実力が測られるところがありましたから。
早見 なるほど。ノンフィクションの場合、その場の一次情報を入れたところで本になる頃には古びてしまいますものね。
鈴木 そうですね。だから今は、それよりももっと普遍的なことを書こうという意識が強くなりました。
早見 ちなみに僕が先ほど口にした、書き手である自分自身を剝き出しにする、というところは意識してやられていますか?
鈴木 僕はずっと記者をやっていたので、最初は自分を出さない書き方をしていたんです。新聞記事では自分の主観を出すことはまずないので。ところが、『嫌われた監督』の第一稿を読んだ編集者から、「読者が最も共感するのは、一般人である鈴木さん自身の感情ですよ」と言われて、はっとしたんです。
早見 まさにそれがあるのとないのとで、ノンフィクションは全然変わりますよね。
鈴木 でも長年の手癖があるので、自分を出すことに当初はすごく抵抗があったんです。それでも落合さんのような特別な人の世界観に共感してもらうには、読者が気持ちを付託できるところが必要で、それなら自分自身の弱さやダメさ加減を前面に出してもいいのかもしれないと考え直しました。
早見 結果、鈴木さんはこの作品の中で、これでもかというくらい自分の弱さみたいな部分を吐露しているじゃないですか。そういう等身大の人間が、落合というバケモノに向かっていくところが僕は小気味よく感じました。
鈴木 実際、そう割り切ったら、なんだかすごく楽になりました。