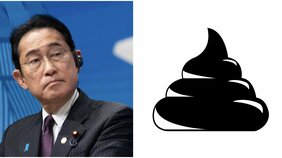若者が損をしてしまう可能性
一方、中高年世代は年金等の給付を受けることになるため、相対的には、やはり若者世代ほどの負担にはならない可能性が高いという。
「消費税減税は、このような税負担の先送りにより、税負担の世代間格差が生まれる可能性があります。将来的な増税を避けるためには、継続的に費用を抑える行財政改革を実施していかなければなりません」
さらに消費税減税には、制度運営や事業者側の混乱といった実務的な問題もつきまとうと髙辻准教授は指摘する。さまざま問題のうち、とくに「事務負担の問題」「飲食店で実質税負担が重くなるリスク」「景気の反動減リスク」の3つをあげた。
「仮に2025年時点で消費税減税を実施する場合、野党などの提案をみると、1年限定で食料品のみ消費税をゼロにすべき、との内容があります。実施すれば、一時的には景気浮揚策としては効果があるかもしれません。一方で、1年間で0%にして、その後に税率を戻すとなると、関連の事務負担が増えてしまいます」
さらにたとえば、食料品のみ消費税をゼロにすると、飲食店の場合は、野菜や魚などの仕入れ時には消費税を払っているものの、お客から取る売上の消費税はゼロになる。それゆえに、仕入れ控除でその分を相殺できず、結果的に税負担が増えるリスクがあるという。
「1年限定では、実施後の景気の反動減のリスクも増すことになります。消費税減税を実施する場合には、『財源をどうするのか』『減税後の対応をどうするのか』『行財政改革をどう進めるのか』の3つの視点でのリスク対応が必要でしょう」
一見するとわかりやすく優しい政策に思える消費税減税。けれど、そのツケが誰に回るのかを考えないと、本当の「公平さ」は見えてこない。
取材・文/集英社オンライン編集部