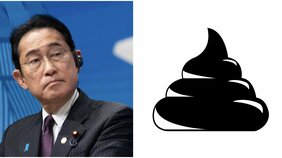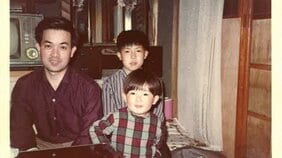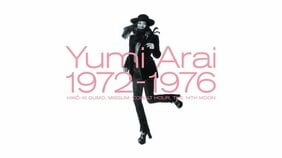“優しい減税”の落とし穴
家計の負担を軽くすることで、消費活動を促す効果が期待される「消費税減税案」。一見すると、国民全体に恩恵がある“優しい政策”に思えるが、実は「世代間の公平性」という観点から、強い批判の声も上がっている。
実際、現役世代は消費税に加えて、給与から厚生年金保険料や健康保険料など、毎月かなりの額を社会保険料として支払っている。一方、定年後の高齢者は年金収入が主で、保険料負担もないわけではないが、現役世代に比べるとかなり小さい。
つまり、消費税を減税すれば、高齢者や外国人の観光客など「他の税や保険料をあまり負担していない層」が相対的に得をしやすく、結果的に社会保障を支える現役世代が、その分を別の形で補うことになりかねないのではないかと指摘されている。
SNS上でも、この点を問題視する投稿が相次いでいる。
〈消費税減税とか論外だろ、あり得んよ 最強の公平性ある財源だぞ〉
〈見た目は全国民に優しいけど、中身は若者いじめだよ〉
〈消費税減税とか高齢者優遇の最たるものだよな〉
〈今の物価高で消費税減税とか消費税廃止なんてしたら観光地はほぼ全て消し飛ぶぞ。爆買い観光客外国人から合法的に税金吸える手段も減るしどう見ても悪手〉
こうした懸念について、目白大学経営学部の髙辻成彦准教授は「減税によって将来世代への負担が増えるリスクがある」と話す。
「仮に2025年時点で消費税減税を実施した場合、先ず、減税した国の財源をどのように確保するのかが問題になります。国債で賄うなどの対応でその場はしのげたとしても、日本は中高年世代が増えている状況にあるため、社会保障費の負担が今後も増大することが見込まれています。
また、財政運営上、社会保障費等の増大する費用の財源を確保するために、結局は消費税を引き上げる必要性が生じてくるため、将来的に現役世代となる若者世代の方々の税負担が増えてしまう恐れがあります」(髙辻准教授、以下同)