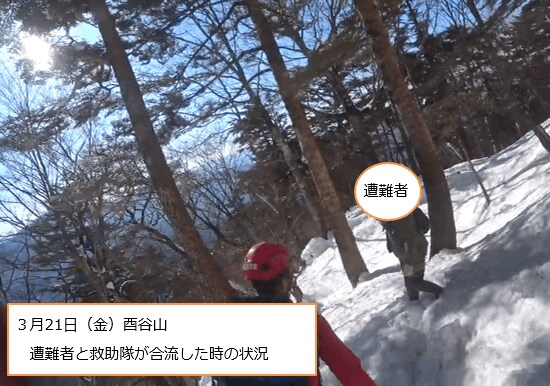無謀な登山を抑止するため、費用の一部を負担させる埼玉県
一方、行政の中にも一部の費用負担を遭難者側に求めるところもある。
懲罰のような費用請求を求める声とは別の次元で、山の安全を考えるうえで参考になりそうなのが、埼玉県が条例に基づき2018年1月から始めた山岳遭難でのヘリ出動の費用の一部を遭難者側に求める制度だ。
「県防災航空隊の防災ヘリが県内山岳地帯の6つの指定エリアで救助のために飛行した場合、燃料代に相当する額を『手数料』として遭難者に負担してもらう制度です。当初は5分あたり5000円、昨年4月からは8000円になりました。
制度開始から今年3月末までに有料化地域では34件の救助フライトがあり、手数料の平均は約6万6000円、平均飛行時間は1時間程度になります」(県消防課)
この条例は2010年7月に県防災ヘリが秩父市の山中で遭難者の救助活動中に墜落し乗員5人が死亡した事故を背景に生まれた。
「現場は地上から救助隊を送っても到着に時間がかかり、ヘリ救助も難しい場所でした。これを機に、登山者に危険で救助する側もリスクが高い地域での救助の有料化の議論が始まりました。難しい選択でしたが、無謀な登山を抑止するためにも、ガイドブックに『上級者向き』と書かれているような難しいエリアを6か所指定し、始めたのです」(県消防課)
その狙いは当たったのか。
「少なくとも6地域でのヘリの救助飛行件数は、条例施行前の4年間が41件だったのに対し、施行後4年間は24件と減りました。これは県内全域での同時期の山岳救助飛行が78件から68件に減ったことと比較しても減少幅は大きいです。
お金を取るだけでなく危険地帯を知らせるチラシを配る事故防止キャンペーンも続けています。そうした全体の取り組みの結果でしょう」(県消防課)
条例施行後、埼玉県には他の自治体からも問い合わせが相次いだが追随するところはなかった。しかし、「富士山の今回の問題が報じられた後、有名な山を抱えるある県から条例の問い合わせが来ました」と消防課の担当者は話す。
富士山は外国人観光客の人気も高まっている。山梨県側のふもとのタクシー運転手は「年々増えて、去年は山開き中にタクシーで5合目まで行く人の半分は外国人でした。英語圏の人が多いけど中国のかたも全体の2、3割はいると思います」と話す。
美しい山を悲劇の現場にしないため、外国人も含めた登る側の自覚が求められている。
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班