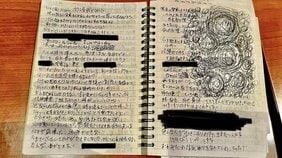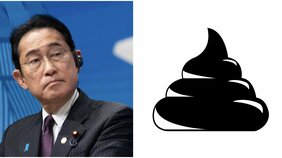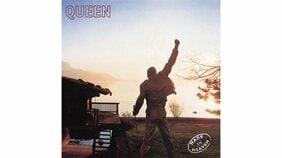「創立時の理念として、女子教育の重要性を説いてきました」
2023年3月には、東京都多摩市にある恵泉女学園大学・大学院が閉校に向けて24年度から学生募集を停止すると発表。
大学は「18歳人口の減少、とくに近年は共学志向など社会情勢の変化の中で、入学者数の定員割れが続き、大学部門の金融資産を確保・維持することが厳しくなりました」と説明していた。
ことし2月には、名古屋市昭和区の名古屋柳城女子大を運営する学校法人が、来年度から学生募集を停止すると発表した。同校は2020年4月に開校し、昨年3月に1期生が卒業したばかりだった。
もちろん、女子大も手をこまねいていたわけではない。新学部・学科の開設で志願者を取り込む動きは京都の女子大でも30年前から始まっていた。1994年に光華女子大が、97年に京都橘女子大が、それぞれ新学科を開設すると全国的な話題を呼んで志願者が増え、他の女子大も追随する動きが出た。「最近もデータサイエンスや環境などを学ぶ学部・学科を新設する動きは続いています」と全国紙記者は話す。
こうした変化で魅力を高めることに成功できるか。または男子学生を受け入れ共学化するか。女子大が生き残るにはこの2つの道しかないように見える。
京都ノートルダム女子大は共学化による生き残りは考えなかったのか。担当者は「本学の創立時の理念として、女子教育の重要性を説いてきました。その中で共学化の選択肢を敢えて取りませんでした」と説明した。
大学の街、京都から名門校が消えることで、大学運営の厳しさが改めて浮き彫りになっている。
※「集英社オンライン」では、今回の記事についてのご意見、情報を募集しています。下記のメールアドレスかX(旧Twitter)まで情報をお寄せください。
メールアドレス:
shueisha.online.news@gmail.com
X(旧Twitter)
@shuon_news
取材・文/集英社オンライン編集部ニュース班