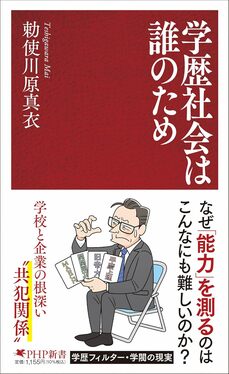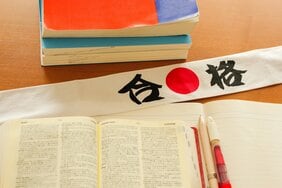「能力」が高い人こそが、「価値」が高い人
こうして誕生したのが、努力を含む「出来」(=能力)によって、分け合い、つまりもらいの多寡を決めましょう、とする能力主義でした。
頑張れて、人よりできることが多い人、つまり「能力」が高い人こそが、「価値」が高い人である、と。そしてこの、「価値」が高い人が多くをもらうべきである─とするロジックは、現代社会でおよそその理屈を疑われることなく21世紀を迎え、いまだに私たちの社会システムの中心的な運用基準(=主義)となっています。
個人の「出来・不出来」を把握し、他者と比較したうえで、序列/優劣をつけることで、取り分に傾斜をつけることを合理化するのです。繰り返しますが、すべては限りある資源のため。本当は大盤振る舞いしたいところですが、支援やケアする対象は能力によってやむなく「絞られる」わけです。
と同時に、近代化以降、「もらい」とは、多くの日本人にとって、仕事をすることで得る対価(給与などの報酬)を指します。自分で商売をする人もいれば、企業に雇用されながら、給与所得の形で「もらう」ことがごく当たり前になりました。
その配分される給与をもとに、買い物に行って食品を得るし、お金を出して不動産会社から土地や建物を購入したり、借りたりする。いまの私たちにとってごく当たり前の社会システム、インフラとも言えます。
ちなみに先ほど、「およそその理屈を疑われることなく」と述べましたが、正確には一部に疑ってくれる学問も存在しています。
それは私も修めてきた教育社会学です。それでも一般的に言えば、この「できる人」「価値の高い人」が多くをもらえば文句ないでしょう? という能力主義のロジックよりも人びとの納得感を誘う論理は、いまだ見出されていません。
今日も会社では、「誰が『できる人』なのか?」で評価がなされ、給与やボーナスといったもらいの多寡、言い換えれば個人の「稼ぎ」(配分)が決定されていますから。
文/勅使川原真衣 写真/shutterstock