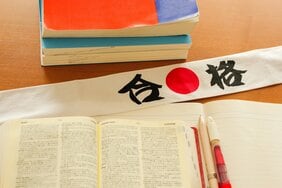人の価値を「評価」する?
天は人の上に人を造らず、天は人の下に人を造らず─福澤諭吉の言葉であることはあまりに有名ですが、要するに人は皆平等なのだと、幼いときに私も教わりました。「人の価値」に貴賤はないという意味だと、一般的には捉えられています(福澤の真意とは異なるのですが)。
でも誰もが知る学歴主義・学歴社会という言葉を紐解こうとしたら、これまた誰もがしばしば耳にする「人の価値を評価する」という話にぶち当たりました。一人ひとりの命に貴賤はないはずですが、あたかも上等なものとそうでないものがありそうなニュアンスの漂う「価値の評価」という言葉。これが意味するものを解きほぐしたいわけですが、私はここで、その是非に焦点化するのではなく、
そもそもなんで「人の価値」を「評価」しなきゃいけないんでしたっけ?
という点から掘り下げてみようと思います。
誰かが誰かの「価値」を「評価」しないと、なぜいけないんでしょうか。拙著を何冊かお読みの方には恐縮ですが、人が人の「価値」を序列づける根本的な背景を考える際には、能力主義の理解を避けては通れません。よって重複した議論になることをご容赦願いつつ、能力主義の基本概念を紐解いておきましょう。
非常に明快な話です。お金も土地も食料も……有限です。だから分け合って生きなければいけません。となると問題は、それをいかにして分けるか(配分)になりますが、かつての身分制度の時代は、名家出身者などの権力者には多くをあげましょう、とかいうことがまかり通っていたわけですね。配分といっても力の大きさ(既得権益)に隷属する形です。
しかし社会の進歩とともに、「本人がどうすることもできない、つまり『生まれ』で持てる者と持たざる者が決まってしまうのは不平等ではないか?」との疑問が湧いてきます。じつに民主的な響きです。
そして近代化に伴い、廃藩置県、四民平等が公布され、身分制度は廃止されました。と同時に、代々就いている職業も違えば、当然所有している財産にも差があるなかで、どうすればできるだけ不満の出ないように、納得感を担保しながら、平等に配分できるか。この課題にいよいよ光が当たるようになったわけです。(詳しくは士族授産事案からの士族学校の興りなどを経ます。天野郁夫氏の歴史社会学的知見を参照)