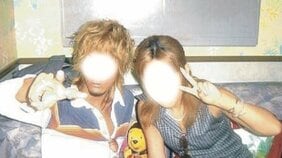トイレの個室に入ったら“モラル頼み”
科学・医療ジャーナリストとして、若手研究者のキャリア問題や捏造・改竄といった研究不正などを主なテーマに執筆活動を行っている榎木英介氏。
現在は大学教員の職を辞しているが、過去には屈指の志願者数を誇る私立大学に教員・講師として勤め、そこで大学入試センター試験(当時)などの試験監督を担当した経験もあるという。
「私が務めていた大学のように春先にいくつも試験がある総合大学では、輪番的に若手教員が試験会場へ駆り出されるので、何かしらの試験監督を少なくとも1回以上は経験します。
当然、カンニングのような不正をいかにして防ぐかという問題は、大学にとって非常に大きなテーマでした」
ガラケー時代から試験監督が気を揉んだのが、小型カメラと通信の機能を持つ端末によって、写真や動画を撮影され、試験問題を外部に流出させる不正だ。
昨年は「スマートグラス」のカンニング事件が発覚。メガネ型のほかにも腕時計型デバイスや超小型イヤホンなどを使った海外のハイテク手口にも注目が集まった。
また、今年1月に実施された大学入学共通テスト(共通テスト)の試験中に、試験監督が受験生のトイレ個室に同行した騒動もあった。
率直に「不適切だ」という感想を抱く一方で、試験中でも個室トイレの中は監視の目が行き届かないという事実に改めて気付かされるような話ではある。
「実際、身に付けられる小型カメラや通信機能を使うかたちで手口が巧妙化していくと、人間の監視で見破ることは非常に難しいです。
時計なども日本の試験監督者が警戒するポイントのひとつですが、基本は受験者のモラル頼みで現状の対策では限界があります。
そもそもトイレの個室では、アナログなカンニングペーパーもバレずに見ることができる。
確かめようのないことですが、発覚する試験の不正は氷山の一角なのかもしれないという懸念は、私が試験監督を担当していた頃から感じていました」