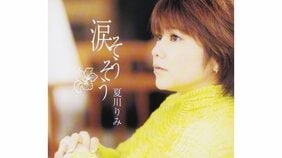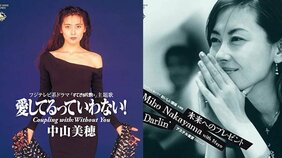『上を向いて歩こう』はなぜ人の胸を打つのか
論理的に正しいことを言われても余計に悲しくなったり頭に入ってこないということはないだろうか? 励ましの言葉は特にそうかもしれない。でも、同じ言葉なのに、歌になったらすっと心の隙間に入ることがある。
3・11のあと、いろんなところから坂本九さんの『上を向いて歩こう』が流れた。この曲は、1961年に誕生し、戦後日本の復興から高度経済成長期という激動の時代を支えてきた日本の代表的な歌謡曲だ。
台湾に旅行に行ったときにもタクシーの中で流れていて、運転手さんが口ずさんでいたことにも驚いたし(ちなみに、千昌夫の『北国の春』も歌っていた)、海外でもこの曲だけは知っているという外国人も多く、日本の歌謡曲の中では最も認知度が高い曲じゃないだろうか。
上を向いて 歩こう
涙が こぼれないように
思い出す春の日 一人ぽっちの夜
具体的に何があって涙がこぼれそうなのかは書かれていない。春も夏も秋も涙がこぼれないように上を向いて歩くというとてもシンプルな歌詞だ。
でも「泣きながら歩く一人ぽっちの夜」というフレーズ。結局泣いているんです。
リスナーは、主人公が上を向きながらも涙を流していることに救われたのではないか。そして、「あなたは一人じゃないよ」とは言わずに、「一人ぽっちの夜」と言い切ったからこそ、みんな、自分だけではないと思えたのではないだろうか。
「人生にはいいことも悪いこともあるんだから前向きにがんばろうよ」とか「ときには泣くことも必要だ」とか「僕もこんなことがあって悲しいんだよ」とか、説教じみたことを言ってない。良い歌詞には余白があるな。書きすぎず、それぞれに想像を委ねる余地のある歌詞だ。
「前を向いて歩こう」ではなく「上を向いて歩こう」なのがいい。論理的にこの歌詞を分析するなら、そもそも上を向いて歩いたら転ぶだろってなるんです。
でも、「上」って言葉のまとっている雰囲気が、みんなに伝わったのだと思う。「前」という現実的な言葉だと、道がどこまでも続く絶望感も想像してしまう。
でも「上」には空しかない。同じ空の下で、みんなでがんばるんだと思えたんじゃないかな。広まっていく歌詞の多くは論理の対極で、空気をたっぷり含み、個性に個性が重なったものなのだねぇ。