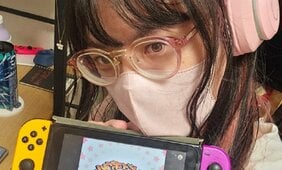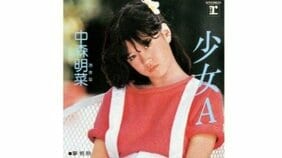肩書きに偽りなし。音楽ゲーム”博士”なRTA走者
RTA(リアル・タイム・アタック)とはスタートからクリアまでの実時間を競い合うゲームの遊び方だ。アクションからパズル、はては音楽ゲームまで、どんなゲームにもRTAプレイヤーは存在し、日夜1分1秒を争っている。
そんなRTAイベントとしては国内最大級を誇る「RTA in Japan」。夏と冬、年に2回開催される同イベントで、2024年・冬、会場も配信のコメント欄もおおいに盛り上げたRTAがあった。
元プロゲーマーのYUDAI氏による「Dance Dance Revolution STRIKE」の約4時間にわたるRTAだ。そんなYUDAIさんに話を聞いた。
――「Dance Dance Revolution」(以下、DDR)90年代後半にゲームセンターで一世風靡した大ヒットゲームですが、その魅力はどこにありますか。
YUDAIさん(以下、同) DDRは非常にシンプルな音楽ゲームです。曲に合わせて上下左右の矢印が流れてくるので、適切なタイミングでボタンを押し、高得点を狙う。最大の特徴は、足で操作することですね。ダンスなので。
足元に上下左右それぞれに対応したパネルがあり、画面の表示にあわせて踏んでいくわけです。足でやるからこそ、自然と体も動いて、高揚感も生まれてくる。それが楽しさにつながっているゲームだと思います。
――1998年にゲームセンターで稼働開始し、99年には家庭用も販売されました。
だいたいの友人がPlayStation(ソニー・コンピュータエンタテインメントから発売された家庭用ゲーム機)と家庭用DDRを持っていたような時代です。私も小学生のときに買ってもらいました。
家庭用のDDRは専用のマット型コントローラーが付属していて、それを踏んで操作するのですが、これがまた滑るし、ドスドスしたら下の階に響くし……大変だったな(笑)
――その原体験が、今につながっていると。
人生には確実に影響を与えていますね!一時期、プロとして大会にも参加させてもらいましたし、今の仕事にも関係しています。大学で助教授として勤めているのですが、修士論文や博士論文も音楽ゲームをテーマで書いていて、現在ではある大学の助教として教壇に立っています。詳細はここでは伏せますが、調べたらすぐに出てくるかもしれないですね(笑)
――ゲームで論文ですか!?そんな研究ができる場もあるんですね
大学院に進むまで、まさか音楽ゲームが研究の対象にできて、それを受け入れてくれる大学や学会があるなんて思いもしませんでした。趣味の範囲だった経験がここまで活用できる職場もなかなかないよなと、数奇な運命に感謝するばかりです。
もし、進路に悩んでいる学生さんがいるなら、「君の趣味も、もしかしたら研究になるかもよ」と伝えたいです。