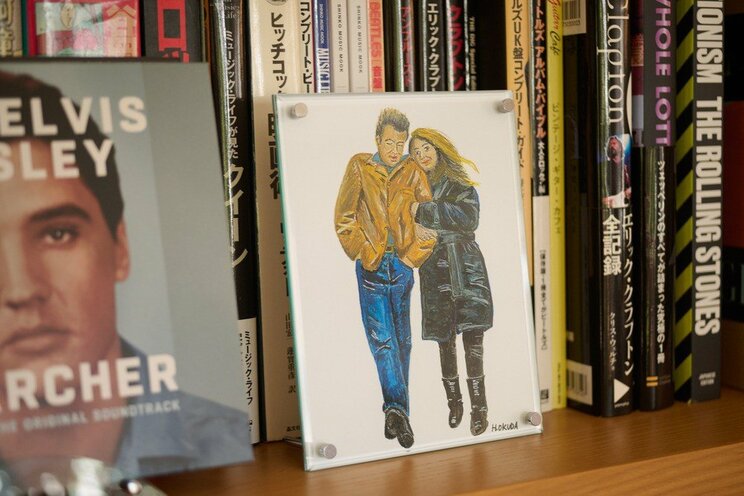視点人物は下の名前で書く
――平塚健太郎絡みで、篠田という犯罪心理学者が登場します。風変わりな人物で面白かったのですが、彼は下の名前が出てきませんよね。姓で書かれる人物と下の名前で書かれる人物とがいるのは。
奥田 下の名前で書いているのは、その人物の視点で書いているときですね。群馬県警の若手刑事で斎藤一馬という人物が出てくるけど、「斎藤一馬」と登場時に書いて、斎藤一馬の視点で書くときは、「一馬は」と書く。ほかの人の視点で書くときに出てきたら「斎藤は」にする。原則としてはそうですね。例外もあるけど。
『リバー』には主な視点人物が六人出てきます。斎藤一馬と栃木県警の野島昌弘、元栃木県警の滝本誠司、中央新聞の千野今日子、十年前の事件の被害者遺族の松岡芳邦、スナック「リオ」の吉田明菜。六人くらい出すと、読者が追い切れなくなって、もっとたくさん視点人物がいるように見えてくる。篠田の視点では書いていないから下の名前もとくに書かなかったというわけです。
――たしかに下の名前で書かれると登場人物との距離がぐっと縮まって、事件に向けるまなざしも変化しますね。視点人物の中では松岡芳邦も強烈な印象を残します。十年前の事件で娘を亡くしていて、遺体発見現場の不審人物を見張り続けています。十年ぶりに起きた事件にも自ら関わっていって並外れた情熱を注ぎ込みます。
奥田 かなり前ですが、池袋駅で立教大生が殺された痛ましい事件がありましたよね。駅のホームで殴られて亡くなってしまって、犯人が逃亡したまま捕まっていない。被害者のお父さんがそのあとも犯人を捜し続けているというルポルタージュ番組をテレビで見て、ずっと頭に残っていたんです。
――松岡の場合は目の病気があって、視力を失う恐怖とも戦いながら犯人を追う。その切実さに胸を打たれました。書いているうちに、もともとイメージしていた登場人物みたいなものが違う顔を見せていくこともあるんですか。
奥田 ありますね。書いているうちにだんだんそれぞれのキャラクターがひとり立ちしていくというかね。自分の都合のいいようには動かさないから。「この人、この次何やるんだろう」と思いながら書いていますよ。
――今回、意外な動きをした登場人物はいますか。
奥田 滝本をあんなふうに書くつもりはなかったですね。頑固おやじみたいな昔気質の元刑事のつもりで考えていたんだけど、どんどん自分で動いていって。まあでもやっちゃうだろうなっていう予感はあったかな。
――すごい展開でしたね。池田みたいな狂気に対しては、追う側も狂気にならないと対抗できないんだと感じるくらい。警察は権力ですから暴走されては困りますが、捜査している刑事の実感としては、「あいつを野放しにしておけない」という思いもあるんだろうなと。池田以外にも有力な容疑者が浮上しますが、本当に彼が犯人なのか。刑事も読者も最後まで翻弄されますよね。何より動機が見えてこない。
奥田 よく「犯行の動機解明にあたる」って言うけど、そんなのわかるわけがないっていう思いが僕の中にあるんですよ。思い描いた人生を送れなかった人間が世の中に対して何かやってしまうっていうのは世間にたくさんありますよね。アメリカの銃乱射事件もそうでしょう。そういった犯罪に対して動機自体の解明って意味がないと思う。できるのは、誰も孤独にさせてはならない、社会の援助をどうするかというのが重要なんじゃないかというくらいで。だから今回も犯人の内面に関してはほとんど描写していません。犯罪に関してわかったようなこと書くのが嫌だったからあえて書かなかったんです。
――作中でも書かれていますね。「マスコミはいつも、動機の解明が待たれますという常套句で犯人像を探ろうとするが、理屈で説明できる人間なら人など殺さないのである」。なるほどと思いました。でも、納得できないと不安だからマスコミに動機を決めてもらって物語に落とし込んで安心したい。事実を報道するはずのマスコミが物語化を志向して、小説家の奥田さんがそれを否定するんだなと思うと、面白く感じます。


「何を書くかわからない」は既得権
――群像劇ということで、脇の登場人物の印象が濃いのも奥田さんの作品の魅力です。今回、個人的に長野の八木というラーメン屋店主が好きでした。元ヤンキーで地元でやたらと顔が広い。警察の捜査にも積極的に協力します。
奥田 僕は岐阜出身なんだけど、故郷に帰ると昔ヤンチャしてたのが顔になっていたりするんですよ。顔になってるっていうのは別に悪いことをしているわけじゃなくて、地元で会社を経営してて羽振りがいい。「何でもやってやるぞ」みたいな景気のいいことを言ったりね(笑)。
――人物像に心あたりがあるんですね。では、一方、池田みたいな犯罪者気質の人間はどうですか。
奥田 いない、いない。映画からヒントを得ていますよね。犯罪者が出てくるような映画、リアルな人間を描いた人間ドラマが好きだから。テレビドラマでいうと、僕はずっと山田太一さんが好きなんだけど、ああいう市井の人を一人の人間として描いたものが好きなんです。自分でもそういうものを書きたい。市井の人の中には池田みたいにはみ出してしまう人も当然いるわけです。
でも今、そういうリアルな人間を描くって少数派でしょう。日本人の七割がアニメとアイドルとゲームで育ってるというのが僕の実感で、そうするともうリアリズムって用がない。舞台設定とプロットとキャラが大事。それはつまり、テーマパークのアトラクションですよね。僕はそういうものにまったく関心がない。自然なものをやりたいんですね。
つまり、「テーマパーク」に対して「自然の森」を僕は書きたいと思っているんです。自然の森に読者を案内している。だからそこに人工的なアトラクションはないわけですよ。風とか小鳥のさえずりとかをただ楽しんでいただければと思うんだけど。
僕も完全なオールドスクールで分が悪いなとは思いますけど、少数派には少数派の矜持があるしね。
――奥田さんの場合は、『リバー』のように犯罪を扱ったものもあれば、日常寄りのユーモラスなものやちょっとファンタジックなものもある。その幅広さも興味深いところです。
奥田 同じようなものを書かないのはルーティーンが苦手だっていうのと、あと、読者の期待に応えたくないっていうのがあるかな。
ヒット作って、作家にとって諸刃の剣なんです。それと似たものを読者も編集者も求めてくるから、応えていたら疲弊するし自己模倣が始まる。そうなる前に別のことをやるわけです。だからデビューしてすぐの段階でいろんなことやっちゃったほうがいいんですよね。そうすれば既得権になるわけです。「奥田は何書くかわからない作家だ」っていう。そうなれば楽ですよ。若い作家の人にぜひ言いたい。「読者と編集者の要望に応えてはならない」って(笑)。
――私は最初に『最悪』を読んですごいと思って、次にさかのぼってデビュー作の『ウランバーナの森』を読んだんですが、『最悪』とはまるで違う作品なので驚きました。しかも『最悪』『邪魔』の次が『イン・ザ・プール』。たしかに次に何が来るかわからないですね。
奥田 自分の中のルールみたいなのがあって、それに従ってやっていれば、読者はついてきてくれるんじゃないかって思っていますね。