朝日新聞社はリアル版『半沢直樹』の世界!?
――読者からはどんな反響が多かったのでしょうか。
鮫島 この本は政治やジャーナリズムが題材なので、同じマスコミ業界の読者が多いのかなと思っていたら、意外とサラリーマンからの反応が大きくて驚いています。企業の生き残り方とか組織のあり方とか、そういう観点で読まれているみたいですね。
中小企業の経営者からもたくさん手紙が届いています。生意気な若手をどう使えば良いか、とかね。僕自身が生意気な記者だったことは、本をお読みいただければわかるかと思います(笑)。あとは組織管理だとか組織運営だとか、そういう企業のマネジメントの観点で読んで、「ああ、うちの会社も似てるな~」みたいな反応も多いです。
――「吉田調書事件」への対応では、社長の面子を忖度するあまりトラブル対応が遅れ、最終的にはすべての責任が現場のデスクや記者に押し付けられるという一連の経緯に仰天してしまいました。
鮫島 先日、元検察官で弁護士の郷原信郎さんと対談したんですが、郷原さんも本書を読んで「朝日新聞と検察はそっくりだ」と言っていました。日本のどの組織や会社にも共通する内向きな足の引っ張り合いと、狭い世界で競い合ってみんなで共倒れしていく様子が生々しく書かれているので、共感を得られたのかな。
――『半沢直樹』にも近いような読まれ方ですね。
鮫島 そうそう。銀行や商社にいる知人たちもみんな同じ反応で。「うわ、どこも一緒だな」みたいな。朝日新聞も検察も銀行も商社も、戦後日本を支えてきた大企業はいまみんな行き詰まっている。その原因が縮図のように描かれているという評価の声もありました。
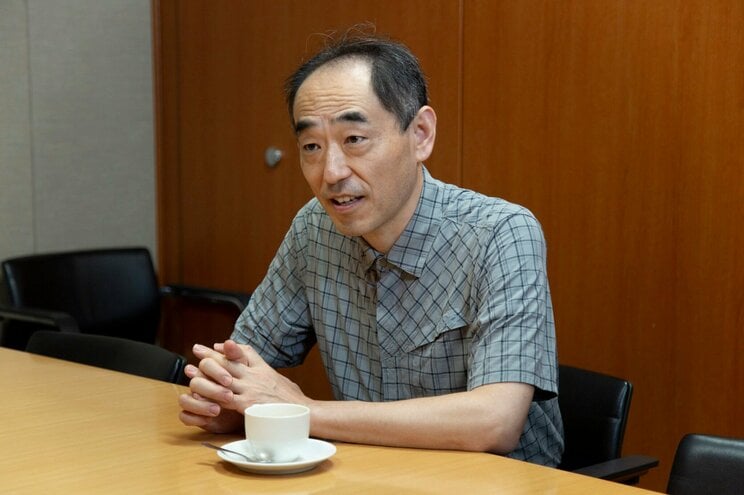
ソニーで結果を出していたのに左遷されて、その後Googleの日本法人代表になった辻野晃一郎さんという方が書評を書いてくれたんですけど、彼も「自分がソニーで経験したこととまったく一緒だ」と言っています。
やっぱり日本がここ30年間ずっとデフレで元気が無いのは、組織の閉塞感や空気と関係があると思うんです。みんなそう感じているから、政治や報道に興味が無い人も手に取ってくれているのかもしれません。そうだとすると嬉しいですけどね。
――ひとつ不思議だったことがあります。新聞は当然ながら読者が読むものなので、「読者目線」ということをもっと意識するのかな、と想像していました。でも本書を読んでいると、ずっと組織内部の論理や忖度ばかりが先行している気がしてなりません。
鮫島 出版社からすると理解しづらいでしょうね。雑誌や書籍は日々の売り上げ部数という数字で左右される世界だから。新聞とは全然違います。
新聞は定期購読で、短期間に部数が上がったり下がったりするわけじゃないから、もともと読者に対して非常に鈍感なんですよ。自分たちの記事が本当に読まれているかどうか、客観的に確認する術もないし、フィードバックも評価も何もない。読者からの手紙も一応あるけど、毎回同じようなマニアの人が書くものが大半です。
そうすると、どうしても自己満足の世界に陥っていくんです。新聞って、一方的に「これは素晴らしい記事だから読め!」と訴えてくる媒体でしょう。しかもなぜ良い記事かというと、「一面に載ったから良い記事に決まっている!」というロジックで。しかしそれは単に内輪の論理で決まっていることに過ぎません。
こういう環境だと、読者に向き合うのではなくて、会社の中で上司にゴマをすって自分の記事を大きく扱ってもらえるようにするといった、社内の根回しや調整に力を注ぐようになっていくんです。それが社内政治を生む土壌になっているんですよ。
確かに、良い記事が必ずしも読まれるとは限らないのも事実です。それでもメディアである以上、どんなに良い記事をつくっても読まれないということは何かが足りないわけだから、やっぱり反省して色々と考えなきゃいけない。それが真の意味での読者との対話だと思うんだけどね。
























